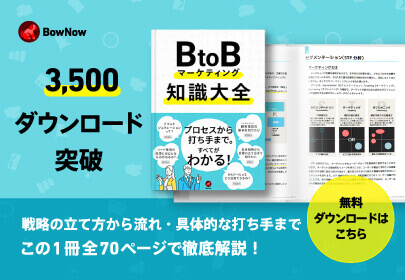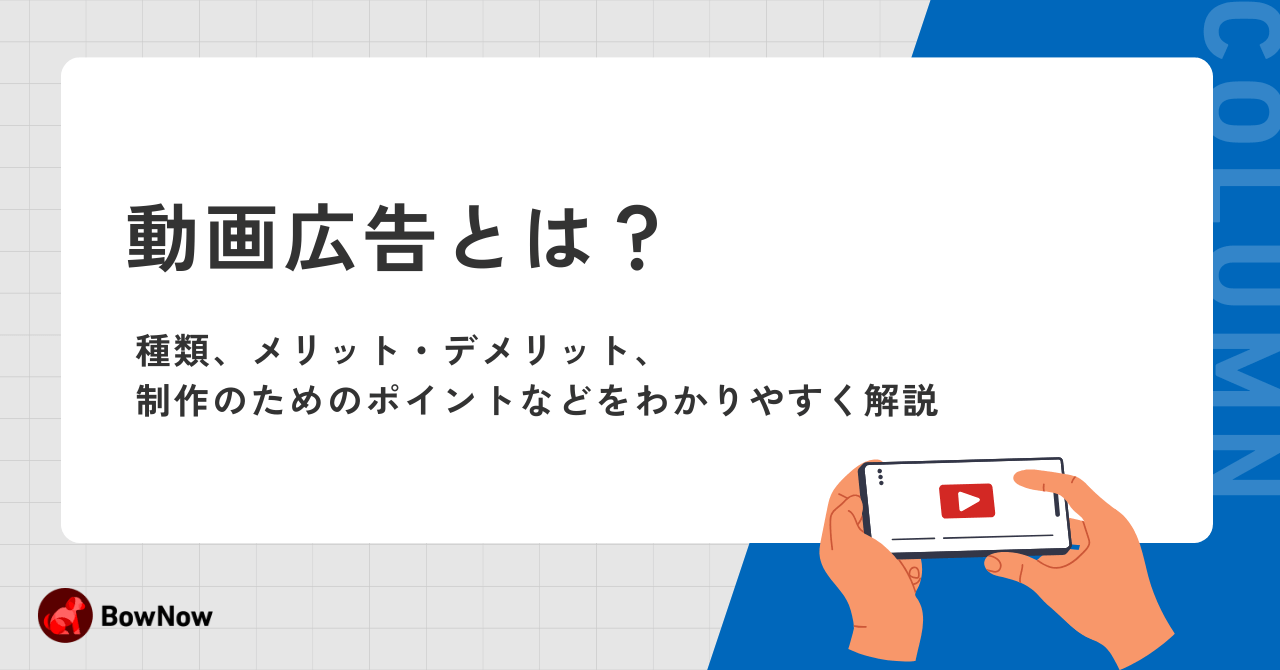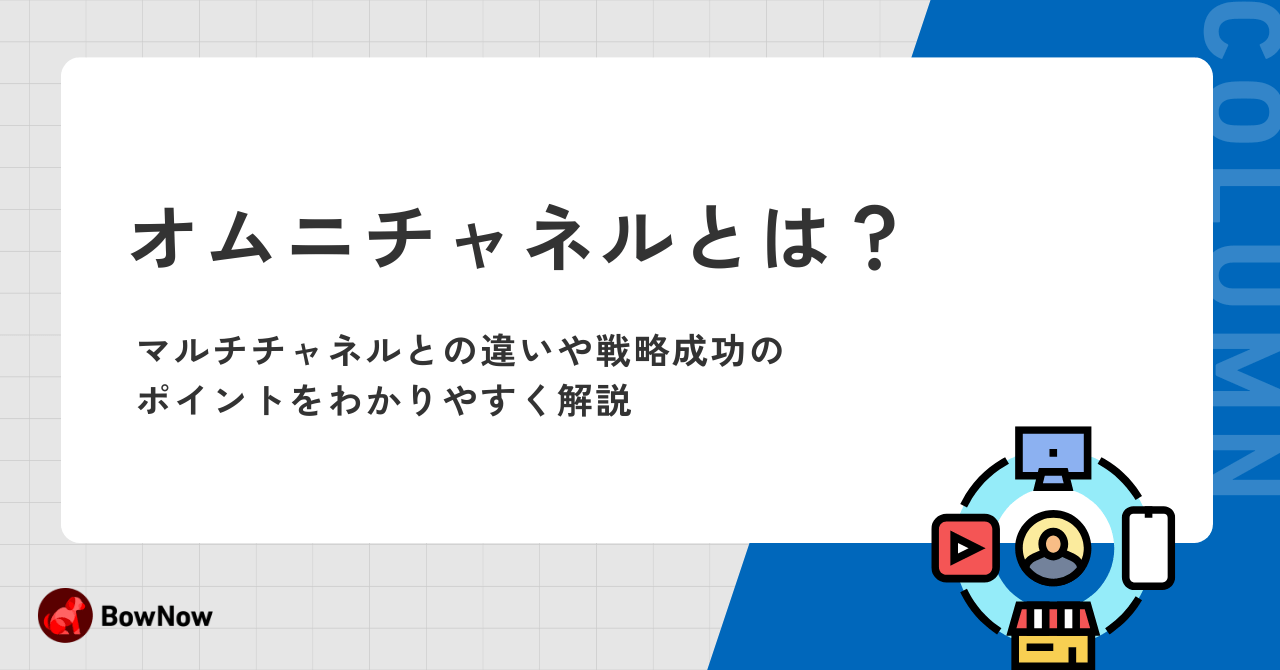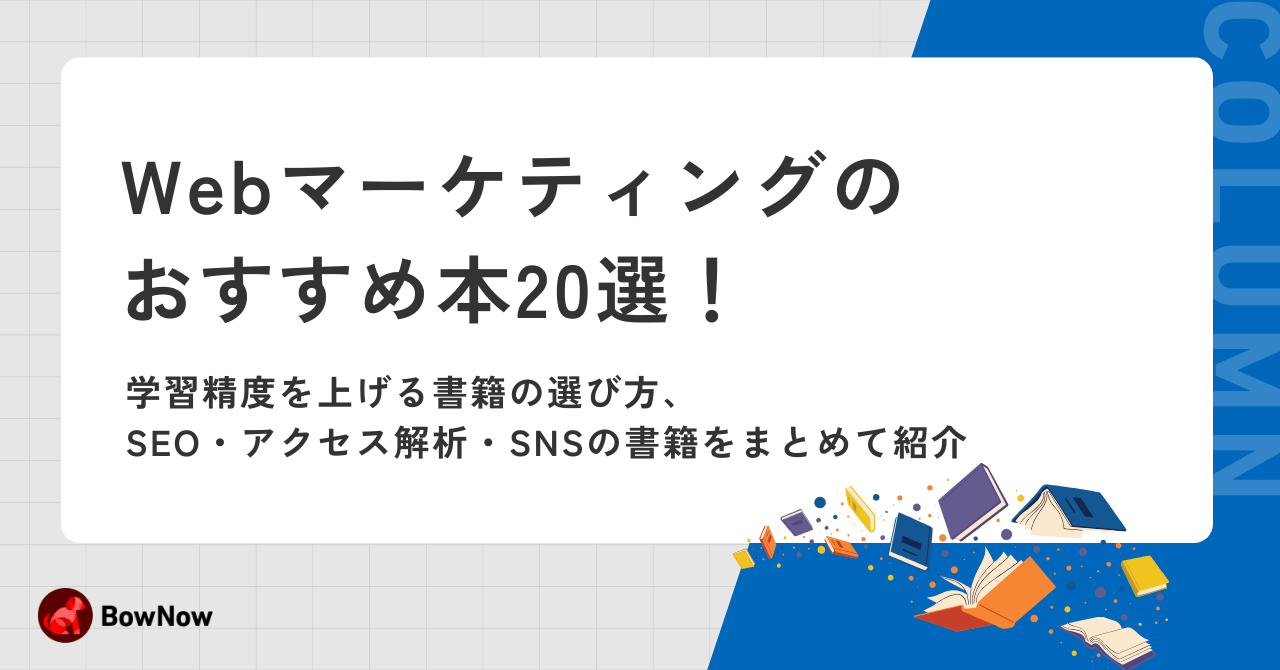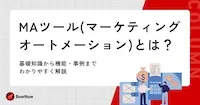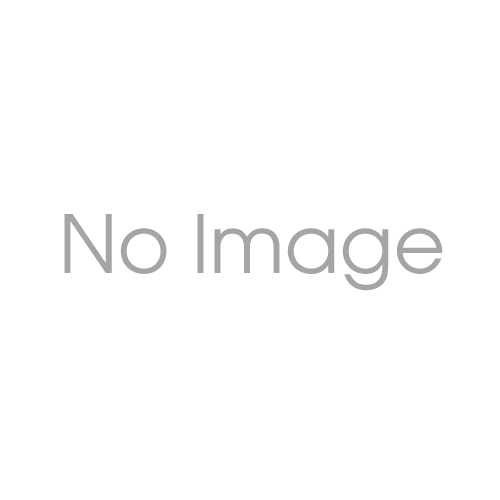ABテストとは?成果につながる進め方やコツ・事例、役立つツールも紹介
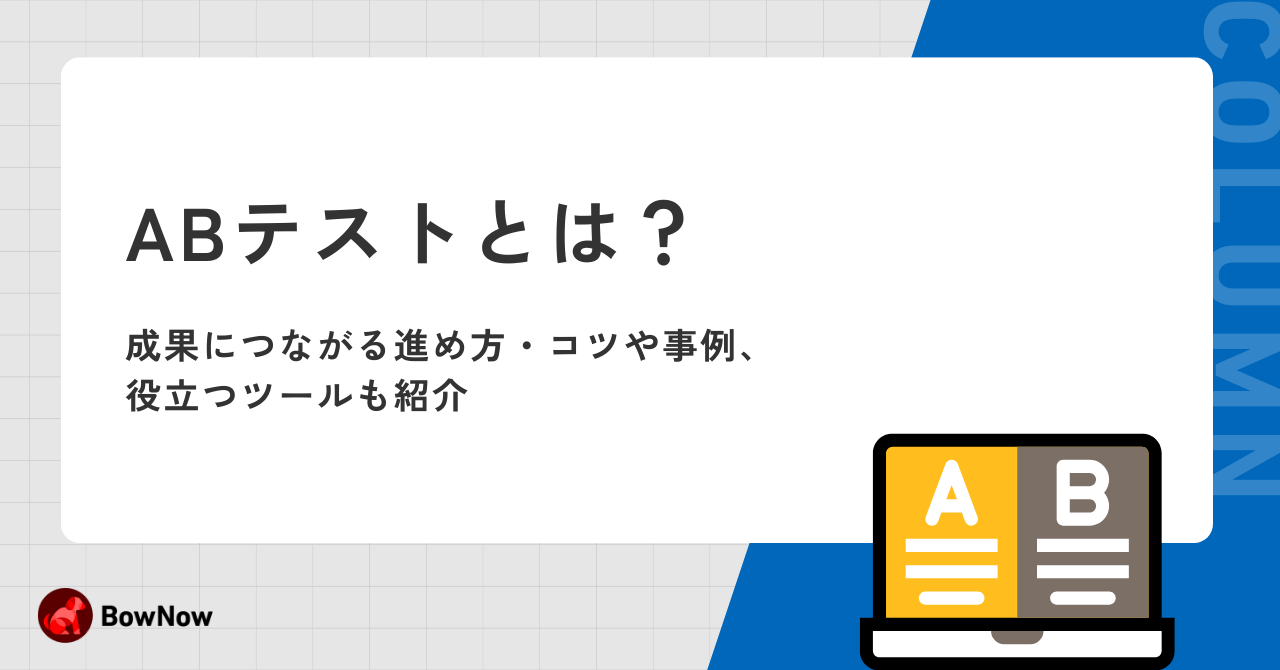
「ウェブサイトのコンバージョン率を上げたい」「広告の効果を最大化したい」という課題を解決する鍵が、ABテストです。勘や経験に頼った改善では、時間もコストも無駄にしてしまう可能性があります。ABテストを行えば、データに基づいた明確な根拠を持って、顧客の行動を最適化できます。
この記事では、ABテストの基本から、成果を出すための具体的な進め方、事例、さらには無料で使えるものから高機能な有料ツールまで、幅広く解説します。
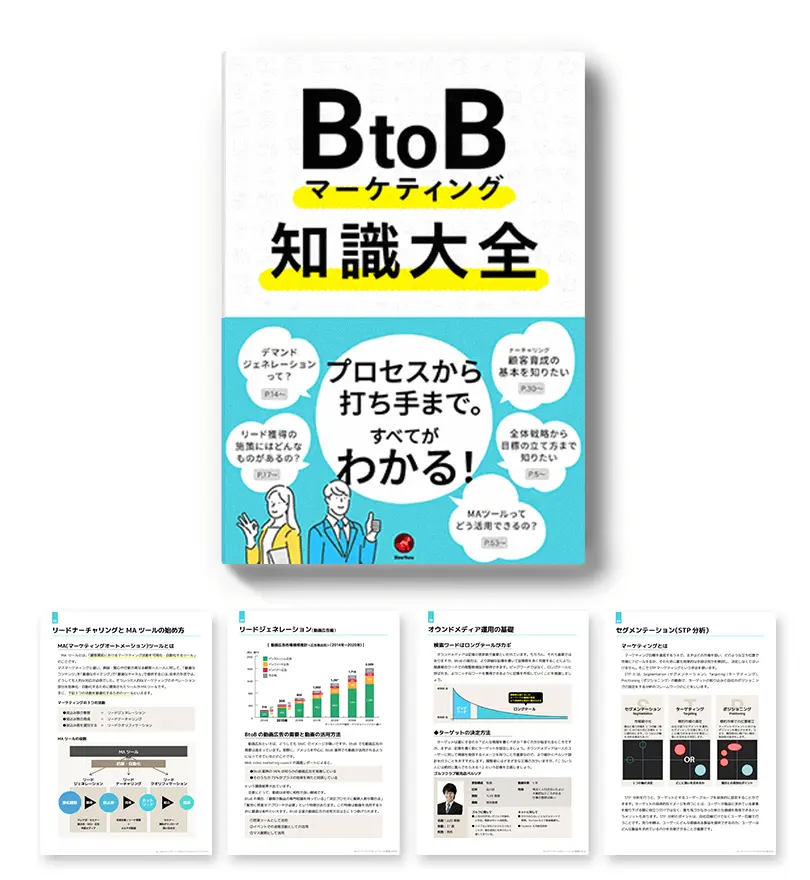
3,500ダウンロード突破!
『BtoBマーケティング知識大全』
BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。
まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。
目次
ABテストとは?目的と役割
ABテストとは、複数のパターンを比較検証し、どちらがより高い成果を生み出すかを見つけ出す手法です。たとえば、ウェブサイトのデザインや広告の文章など、特定の要素を変更したAパターンとBパターンを用意し、どちらがより良い成果を生むかを測定します。ウェブサイトのデザインやレイアウト、広告のコピーや画像、メールマガジンの件名や本文、アプリケーションのユーザーインターフェースなどさまざまな場所で利用されています。
ABテストの主な目的は、以下3つです。
|
ABテストは、ユーザーの行動や反応を定量的に分析し、最も効果的なバージョンを特定します。問い合わせや注文、会員登録などの促進に効果的です。また、クリエイティブの最適化を通じて、投資に対するリターンを最大化します。既存のコンテンツに部分的な変更を加えることで、大規模なリニューアルよりも低コストで効果的な改善ができます。推測や直感ではなく、実際のユーザーデータに基づいた客観的な判断ができるようになるのも特徴です。より確実性の高い施策展開へとつなげられます。
ABテストが必要な理由
ABテストを実施する理由は、主に三つあります。
| ①精度を高め、収益を増やす | 感覚や経験則ではなく、データに基づいた改善策がわかる。 広告費や人件費の無駄を削減し、CVRやLTVの最大化につながる。 |
| ②低コストで改善が可能 | ページ全体を作り直すことなく、ボタンの色や文言変更といった最小単位で検証できる。 限られた予算でも実施しやすい。 |
| ③成功パターンを蓄積できる | 検証結果をナレッジとして残すことで、次回以降の施策立案に活かせる。 属人的な判断に頼らず、再現性の高い施策が打てる。 |
最初に作ったホームページや広告、ランディングページは、いわば仮説の集合体です。実際に運用してみなければ、どの要素が成果につながるのかはわかりません。メインビジュアルの差し替え、見出しや文章の書き換えといった工夫で、パフォーマンスが向上する可能性があります。ABテストは、こうしたケースでどの案が効果的かを明確に判断できます。
また、思うような成果が出ないからといって、ページ全体を作り直すのは手間もコストもかかります。一方、ABテストは小規模な変更で実施できるため、大がかりなリニューアルに比べて低コストですみます。少しずつ段階的に改善できる点もメリットです。大きな失敗を避けながら、継続的に改善を進められます。
ABテストを繰り返すことで、「メインビジュアルはこのデザインが効果的」「この言い回しで訴求すれば成約率が上がる」「このバナーを使うと広告のクリック率が上がる」といった知見が蓄積されていきます。こうした情報が集まれば、次の施策をより早く、的確に展開できるようになるでしょう。うまくいったパターンを社内で共有することで、組織全体のマーケティング力の底上げにもつながります。
ABテストのメリット
ABテストは、意思決定の精度向上 → 効果の最大化 → 継続的な改善という好循環を生みます。主なメリットは以下のとおりです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 複数のパターンを同時に検証できる | ボタン色・文言・画像など複数パターンを並行比較でき、どの要素がユーザーの行動に最も影響を与えるかを効率的・客観的に判断できます。各要素の組み合わせによる効果も把握でき、時間を短縮しながら改善案を選定できます。 |
| 低コストかつ短期間で実施可能 | 全体改修は時間もコストもかかりますが、ABテストなら特定の要素のみを変更するだけで検証できます。小さな修正で効果が出れば即適用でき、PDCAを素早く回せます。 |
| 正確な検証結果をもとに意思決定ができる | テスト箇所以外の条件(その他の要素や配信時間、ユーザーの属性など)をそろえて行うため、効果の良し悪しを正確な数値で判断できます。判断の根拠を、ABテストの検証結果から裏付けできます。安易なクリエイティブ変更による費用の浪費や成果外れを防げます。 |
| テスト結果を他の施策にも応用できる | ウェブ広告やLP、メールといった複数接点に展開できる成果パターンを蓄積できます。たとえば「権威訴求が響く」とわかったら、広告や資料、営業トークに展開できます。属人的判断を減らし、再現性ある戦略設計が可能になります。 |
ABテストは、ウェブサイトなどの「部分改善」に強い手法です。ユーザーの離脱が多い箇所や、企業として特に力を入れたい部分に焦点を絞ったり、コピーやメインビジュアルなど要素を絞ったりしてABテストを行うことで、素早い検証と改善が行えます。
ABテストという名前ですが、比較するパターンは二つに限りません。三つ以上のパターンを同時に検証することも可能です。複数のアイデアをまとめて比較することで、短時間でより効果の高い施策を見つけ出せます。
ABテスト4つの種類と使い分けのポイント
ABテストにはいくつかの種類があります。テストの目的や、対象となるウェブサイトの状況に合わせて、適切な方法を選ぶことが重要です。主なテストの種類は以下の4つです。テストを使い分けることで、効率的かつ効果的に改善を進められます。
|
同一URLテスト
同一URLテストは、ウェブサイトのURLを変えずに、特定の要素や見た目だけを変更して比較する方法です。ソースコードを大きく書き換える必要がないため、準備が比較的簡単。そのため、広く使われている手法です。
同一URLテストは、ウェブサイトのボタンの色やテキストの変更、レイアウトの微調整など、小規模な変更を素早く試したい場合に適しています。ユーザーの混乱を最小限に抑えつつ、単一要素の効果を測定したい場合に有効です。しかし、大幅な変更や複雑な機能の比較には向いていません。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
リダイレクトテスト
リダイレクトテストは、テスト対象のウェブページにアクセスしたユーザーを、別のURLに転送して比較を行う方法です。このテストでは、オリジナルのページと転送先の新しいページを用意します。
見た目だけでなく、ページの構造やコンテンツを大幅に変えて比較できる点が特徴です。たとえば、ランディングページを全面的にリニューアルする際に、新しいページの成果を測定したい場合に適しています。ただし、転送による読み込み時間の増加や、検索エンジン最適化(SEO)への影響を考慮する必要があります。また、新しいページの作成や管理にも手間がかかる点に注意しましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
複数ページテスト
複数ページテストは、サイト内の複数ページにわたって変更を加え、その効果を測定する方法です。ユーザーの行動パターンや、サイト内の導線を最適化したい場合に有効です。
たとえば、ホームページから資料請求ページまでの一連の流れを複数パターン用意し、どの導線がより多くの成果につながるかを検証できます。サイト全体のユーザー体験を向上させるのに役立ちますが、テストの設計や実施は複雑になる傾向があります。結果の分析にも専門的な知識が求められるため、場合によっては外部の専門家のサポートが必要になるでしょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
多変量テスト
多変量テストは、複数の要素を同時に変更し、それらの組み合わせの中で最も効果的なものを見つけ出す方法です。たとえば、問い合わせフォームへ進むボタンのサイズ、文言、色の三つの要素についてテストする場合を考えてみましょう。サイズが2パターン、文言が3パターン、色が4パターンあるとすると、2 × 3 × 4 = 24通りのテストパターンが作成されます。この24通りの中から、最適な組み合わせがわかるのです。
多変量テストは、細かな最適化を行う際に有効で、複数の変更箇所がどのように影響し合うかを同時に検証できるメリットがあります。しかし、テストパターンが多くなるため、意味のある結果を得るためには大量のウェブサイト訪問者が必要です。特にBtoBサイトのように、毎月のアクセスが少ない傾向にあるウェブサイトでは、テスト期間が長期化し、改善のスピードが遅くなる可能性があります。そのため、アクセス数の多いサイトや、特に重要なページの最適化をしたい際に行うのが良いでしょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』
この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本
ABテスト実施ステップ・成果を出すための手順とコツ
ABテストで確実な成果を出すには、ただ思いつきでテストを行うのではなく、手順を踏んで計画的に進めることが大切です。ここでは、ABテストを効果的に実施するための5つのステップと、それぞれのポイントを解説します。
ステップ1:テストの目的とターゲットを整理する
ABテストを始める前に、まずは「何を改善したいのか」をはっきりさせることが重要です。最終的なゴールは、問い合わせや購入などのコンバージョンにつなげることですが、小さな改善でコンバージョン率が劇的に変わることはあまりありません。
そこでまず、サイトのアクセス状況やユーザーの行動データを分析し、コンバージョン前の課題を見つけます。たとえば次のような中間目標を設定すると、改善の方向性が見えやすくなります。
|
こうした間接的な改善を積み重ねることが、結果的にコンバージョン率の向上につながります。さらに、ABテストは影響の大きい場所から始めるのが基本です。たとえば、自社サイトのトップページが最もアクセス数が多いのであれば、まずはそこから導線や離脱率を改善すると、全体の成果に直結しやすくなります。
もうひとつの重要なポイントが、ターゲットとゴールの明確化です。「誰に」「何をしてほしいのか」を具体的に定めることで、仮説の精度が上がり、成果の評価も明確になります。「新規顧客のマーケティング担当者に、資料請求をしてもらう」などのゴールを決めてペルソナを設定すれば、、テストの方向性もブレず、スムーズに効果測定が行えるでしょう。
ステップ2:仮説を立ててパターンを作成
目的が明確になったら、次は「どこをどう変えれば効果が出るのか」を考えるステップです。いきなりあちこち変更するのではなく、まずは改善のインパクトが大きそうな箇所を見極めることがポイント。たとえば、以下のような要素はテストの対象として有力です。
|
細かすぎるところをいじるよりも、「目につく・使われる・成果に関係する」部分に絞ってテストする方が、早く結果が出やすくなります。改善対象が見えてきたら、仮説を立てる段階です。
「なぜ今の状態がうまくいっていないのか」「どう変えれば、どんな行動が期待できるのか」この2点をしっかり言語化しておくと、後の評価もしやすくなります。また、“見た目の良さ”にとらわれすぎないことも大切です。成果につながるかどうかは、あくまでユーザーの視点で考える必要があります。たとえば、トップページを改善する場合、こんな仮説が考えられます。
|
こうした仮説は、テスト設計の軸になる非常に重要な要素です。目的に照らし合わせて「本当に効果が見込めるか?」を意識しながら、パターンを作成してください。
ステップ3:検証条件・環境を整えてテストを実行
テストパターンを準備したら、いよいよABテストの実施です。この段階で大切なのは、テスト対象以外の条件をできるだけそろえること。たとえば、テスト期間や対象ユーザーの属性などを統一することで、変えた要素の影響だけを正確に測定できるようにします。ABテストは、一般的に専用ツールを使って行います。ツールはユーザーごとにランダムに異なるパターンを表示し、結果を自動で集計してくれます。
テスト期間は最低でも2週間以上設けることを推奨します。十分なデータが集まらないと、結果の信頼性が下がってしまうからです。さらに精密な検証が必要な場合は、
|
といった方法もあります。ただし、こうした条件分けは設定が複雑になるため、専用ツールの高度な機能を使うか、専門家に相談するのがおすすめです。
ステップ4:結果を分析し改善案を導き出す
ABテストの結果が出たら、まずは仮説が正しかったかどうかをじっくり分析しましょう。単に「どちらが勝ったか負けたか」だけを見るのではなく、
|
を深く考察することが大切です。このプロセスから、次の改善につながる新たな仮説が生まれます。
| 【例:ボタンの色変更テスト】 仮説:「ボタンの色を変えれば、フォームへの移動が増えるのではないか」 結果:変更後の色の方が、逆にフォームへの移動が減ってしまった 検証:サイト全体の色合いとマッチしていなかった可能性がある。次は、ボタンの大きさを変えてテストしてみよう。 |
テスト結果が良ければ、さらに他のパターンで追加テストを行い、さらなる改善を目指します。結果が悪くても落胆する必要はありません。その結果を踏まえて仮説を練り直し、再チャレンジすれば、より確実な成果につなげられます。
ステップ5:改善後も継続的にPDCAを回す
ABテストは一度行って終わりではありません。テスト結果を分析し改善策を実行した後も、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Action)」のPDCAサイクルを継続的に回すことが重要です。時期やユーザーの動向は日々変わるため、絶え間ない改善が求められます。良い結果が得られた場合は、その成功パターンを他のページや施策にも応用しましょう。
ABテストが活用される代表的なシーンと施策例
ABテストはマーケティングのさまざまな場面で用いられます。
| 活用シーン | 具体的な施策例 | 効果・目的 |
|---|---|---|
| ホームページの改善 | 文章や画像の内容変更 色使いの変更 リンクボタンの位置や文言の変更 |
滞在時間増加や成約率アップ |
| ランディングページ(LP)の最適化 | 見出しや本文の変更 画像の差し替え ボタン配置の変更 複数LPの比較検証 |
コンバージョン率向上 |
| インターネット広告 (バナー・リスティング) |
広告のヘッドライン変更 本文差し替え 画像差し替え |
広告費用対効果の改善 |
| ECサイトの商品ページ改善 | 商品の並び順変更 カテゴリ分類見直し 商品詳細ページレイアウト変更 価格表示やレビュー掲載方法の変更 |
売上増加、顧客単価アップ、 カート放棄率減少 |
| メールマーケティング | 件名の比較 本文内容の比較検証 |
開封率やクリック率の向上 |
ABテストは、ホームページやランディングページ、広告、ECサイト、メールなど様々な場面で効果的に使えます。分析することで、滞在時間や成約率、広告の費用対効果、売上、開封率の向上などが期待できます。
ABテストで効果が出やすい比較対象とポイント
ABテストを始める際、どこから手をつければ良いか迷う方も多いでしょう。ウェブサイト全体のデザイン、コピー、画像、ユーザーインターフェース(UI)、色や余白など、テストできる要素は非常に多岐にわたります。初めてABテストを行う場合は、特に改善による効果が大きい部分から取り組むのがおすすめです。これまでの経験から、ABテストで成果が出やすい要素として、以下の4つが挙げられます。
|
ファーストビューのデザイン・構成
訪問者が最初に目にするファーストビューは、離脱防止の要です。一般的に、ユーザーは3秒でウェブサイトへの興味の有無を判断すると言われています。この短い時間で「自分が見るべき情報がある」と思ってもらわなければなりません。訴求内容は、スクロールしなくても見える位置に表示するのが良いでしょう。特にスマートフォンでの閲覧では画面が小さいため、一目で訴求内容が伝わるように工夫することが大切です。
CTAボタンの色・文言・配置
コンバージョンに直結するCTA(Call To Action:行動喚起)ボタンも、ABテストで高い効果が期待できる要素です。「お問い合わせ」や「資料請求」など、ユーザーに具体的な行動を促すためのボタンです。クリックを促すには以下を意識します。自社のユーザー層やペルソナの心理を想像し、それに寄り添ったデザインや言葉を選ぶことが重要です。
| 色:デザインの中で、CTAボタンが目立つ色になっているか。 文言:クリックすると何が起こるのか、ユーザーにとって魅力的で分かりやすい言葉になっているか。(例:「詳細を見る」より「無料資料をダウンロード」) 配置:ユーザーが自然な流れでCTAボタンを見つけられる位置にあるか。 |

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』
この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本
ページタイトルやコピーの表現
ウェブサイトのページタイトルや、広告、ランディングページのキャッチコピーは、ユーザーの興味を左右します。ほとんどのユーザーは、まずキャッチコピーやページタイトルでウェブサイトや広告の全体像を把握し、興味があるかどうかを判断するためです。
いかにユーザーに響くコピーにするかという言葉の工夫と合わせて、目にとまりやすい文字サイズや色、適度な余白の取り方が大切です。ユーザーの心に響く言葉を選び、その言葉が視覚的に際立つようにデザインを調整することで、クリック率やコンバージョン率の向上が期待できます。
また、広告からの流入を考える場合、広告のクリエイティブとランディングページの内容に一貫性を持たせることも重要です。「間違ったページに来たかも」と違和感を持たれないよう、訴求内容だけでなく、デザインのテイストやカラーにも一貫性を持たせるようにします。
導線設計やフォーム項目の見直し
ユーザーがウェブサイト内で目的の情報にたどり着くまでの「導線設計」も、ABテストで改善効果が高いポイントです。ページ間の移動が多いとユーザーは面倒に感じ、離脱の原因となります。わかりやすい導線を作り、なるべくスクロールやページ遷移を減らすことをおすすめします。
また、見たい情報があっても、そこへたどり着くための導線が分かりにくいと、やはり面倒に感じて離脱の原因となります。そうならないために、ユーザーに分かりやすい導線にし、できるだけページ移動をさせない構成にすることが大切です。具体的には、以下のような改善策が考えられます。
|
フォームもコンバージョンポイントとなることが多いため、改善のインパクトが大きい場所です。。フォームまでたどり着いたユーザーは、ある程度の関心入力の手間がかかるため、ユーザーが面倒だと感じて離脱しやすい傾向がありますが高いと予想できるため、ここでの離脱を防ぐことは非常に重要です。
前の画面に戻ると入力した情報が消えてしまったり、入力項目が一度にたくさん表示されて面倒だと感じさせたりするような、ユーザーに負担をかける機会を減らすことが大切です。郵便番号を入力すれば住所が自動で表示されるなど、ユーザーの入力負担を極力減らし、使いにくさを感じさせない工夫を凝らします。
ABテストを行う際の注意点
ABテストは、ウェブサイトや広告の成果を高める上で非常に有効な手法です。しかし、正しい結果を得て効果的な改善につなげるためには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。これらの点に配慮しないと、誤った分析に基づいた改善をしてしまい、かえって成果が悪化する可能性もあります。
テストは同時期・同条件
|
ABテストを行う際は、複数のパターンを同時に検証することが非常に重要です。もしテスト期間をずらしてしまうと、時期によってユーザーの流入経路や行動のモチベーションが変化し、正確な比較ができません。
|
【時期による影響の例】
|
競合の動き、テレビやSNSの話題、季節の変化など、さまざまな外部要因が時期によって結果に影響を与える可能性があるため、テストは必ず同時期に行い、比較の条件をそろえます。また、比較する要素は、基本的に「一度に1つ」に絞ることが望ましいです。もし二つ以上の要素を同時に変更してテストしてしまうと、どの要素が結果に影響を与えたのかを特定するのが難しくなります。
ボタンの色だけを変えてテストをしたら、次にテキストを変えるなど、1つに絞って実施してください。ただし、複数の要素の組み合わせを検証できる「多変量テスト」を使う場合は、この限りではありません。
テスト期間は最低2週間が目安
|
ABテストの検証期間は、最低でも2週間以上続けるのが理想的です。短すぎる期間でテストを終えてしまうと、結果のブレが大きくなる可能性があります。これは、実施した曜日(平日か休日か)や月のタイミング(月末か月初か)といった違いで、結果に偏りが出てしまうためです。2週間以上テストを行うことで、日々の変動があっても平均的な検証結果を得ることができ、より信頼性の高いデータに基づいて判断できます。
ただし、ウェブサイトの特性によっては、この2週間という基準を柔軟に調整する必要があります。アクセス数が非常に多いサイトでは、2週間未満でも十分なサンプル数を得られる可能性があります。逆に、閲覧数やコンバージョン数が少ないサイトでは、2週間では十分なデータが集まらず、より長期間のテストが必要になるかもしれません。メールマガジンの効果検証など、ウェブページ以外の領域でABテストを行う場合も、それぞれの特性に応じて適切な期間を設定することが重要です。
ユーザー数は統計的に有意な規模を確保
|
ABテストから信頼性の高い結果を得るためには、多数のテストに参加するユーザー数、またはコンバージョン数が必要です。なぜなら、ユーザー数が少なすぎると、個々のユーザーの行動に結果が左右されやすく、全体的な傾向を正確に把握できないからです。
10人のユーザーで行ったサンプル調査と、1000人のユーザーで行ったサンプル調査では、その信頼性が大きく異なります。ウェブサイトの検証であれば、ある程度の妥当性のある結果を得るために、一般的に2,000件以上のコンバージョン数が必要とされています。
ただし、元の閲覧数や、メールマガジンの検証のようにユーザー数が限られている場合など、状況によって必要なサンプル数は異なります。アクセス数が少ない立ち上げ期のサイトなどでは、まず一定数以上のユーザーを獲得するための施策から取り組むことを検討しましょう。もしサンプル数が不足する場合は、テスト期間を延長したり、より多くのアクセスを集める施策を実施したりするなどの対策が必要です。適切なサンプル数を見極めるには、統計的な知識や専門家のアドバイスを参考にすることも有効です。
テストは一度に1要素のみを変更する
|
ABテストで最も重要な考え方のひとつは、「何をしたら効果につながったのか」を明確にすることです。そのため、基本的に一度のテストで変更する要素は一箇所のみに留めます。もし一度のテストでキャッチコピーも、デザインも、画像も、そして行動を促すボタンも同時に変えてしまったら、たとえ成果が向上したとしても、その要因がどの変更によるものなのかを特定できません。一つずつ要素を変更してテストを実施することで、より明確な結果を得て、今後のマーケティング戦略に役立てられます。
ABテストのよくある課題とつまずきポイント
ABテストで良くあるつまずきは以下3つがあります。
|
社内リソースが不足して回らない
ABテストツールには、比較的簡単に設定できるものが多く、マーケティングの専門家でなくても取り組めるサービスが増えています。そのため、自社内でABテストを運用している企業も少なくありません。しかし、ABテストは一度や二度で終わるものではなく、長期的に継続することで効果を発揮します。そのため、テストの計画、実行、分析、次の仮説立案といった一連のプロセスを地道に続けていく必要があります。この継続的な運用が、社内の人員だけでは負担が大きすぎると感じる場合があります。
もし社内だけで運用するのが難しいと感じる場合は、外部の専門家に依頼するのも一つの解決策です。専門家は豊富な経験と知識を持ち、効率的なテスト運用をサポートしてくれます。
仮説のアイデアが出なくなる
ABテストにおいて、適切な「仮説」を立てられるかどうかは、テストの成果を左右する最も重要なポイントです。ウェブサイトの課題となっている部分を特定し、改善に向けてABテストを実施しようとしても、その原因を理解できなければ有効な仮説は立てられません。
テストを始めたばかりの頃はアイデアが次々に出てきても、改善を繰り返していくうちに、思いつく限りの仮説を試してしまい、これ以上アイデアが出てこないという壁にぶつかる企業は少なくありません。この問題に対処するためには、外部の専門家からアドバイスを得ることも有効です。外部に頼らず自社で取り組む場合には、積極的に社外から情報を集めることが重要です。たとえば、以下のような方法が考えられます。
競合のウェブサイトや広告でうまくいっている施策を分析し、自社に応用できないか検討。
デジタルマーケティングで成果を出している企業の成功事例を参考にする。
自社のターゲット層に近いユーザーの動向がわかる市場調査データを収集し、分析する。
自社の顧客層に近い何人かのユーザーに直接インタビューを行い、生の声を聞く。 |
自社のことは社内の人間が最も深く理解していますが、それゆえに固定概念にとらわれがちになることもあります。外部からの視点やユーザーの直接的な声を聞くことで、新たな仮説の発見につながることが多いです。
効果が見えづらくて継続できない
ABテストを実施すれば必ず効果が出るというものではありません。また、仮に効果が出たとしても、劇的に数値が改善されるケースはそれほど多くありません。コンバージョン率改善のためのABテストで、わずか0.1%の向上であっても、それは成功と言えるでしょう。もし月間のウェブサイト訪問者数が100,000人であれば、0.1%の改善はコンバージョン数が100件増加したことを意味します(100,000セッション × 0.1% = 100コンバージョン)。
たとえ思うように成果が出なかったとしても、一喜一憂せずに、どんどん新たな仮説の検証を繰り返していくことが大切です。「この仮説は的外れだった」ということを把握するのも、改善の選択肢を一つ減らすという意味では無駄ではありません。地道に続けていくことで、効果が出る仮説のポイントが掴めてくれば、徐々に自社の「勝ちパターン」が見えてくるようになります。短期的な効果が出なくてもすぐに諦めず、長期的な視点でじっくりと取り組む姿勢が大切です。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』
この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本
ABテストの事例3選
ABテストの事例を3つ紹介します。
ページレイアウトのABテスト事例
株式会社ウィルゲートが公開しているABテスト事例より、ページレイアウトに関するABテストの事例を紹介します。主要商品の関連製品ページで実施したテストです。この関連製品は、メイン商品と合わせて継続的に購入される重要なもので、売上への貢献度も高い商材です。もともと、通販の検索結果のように商品一覧が並ぶページでしたが、訴求効果を高めるために、ページを開いたときにリニューアルされた商品の紹介や、そのポイントを伝える画像が一面に表示されるレイアウトへと変更して、ABテストを実施しました。
| 【テストの目的】 関連製品の購入率を高めること。 【仮説】 商品一覧をページ下部に移動させ、商品概要を最初に表示することで、製品の魅力をより効果的に伝えられ、購入につながるのではないか。 【テスト内容】 ページのレイアウトを変更し、以下の2つのパターンを比較。
【結果】 変更前のレイアウト、つまり「商品一覧が最初に表示されるレイアウト」の方が、コンバージョン率(購入率)と下層ページへの移動率ともに高い結果となりました。 |
元のパターンはスクロールしなくても商品が目に入ります(=言い換えると商品一覧しか目に入らない)が、テストパターンはスクロールしなければ商品一覧が目に入りません(=商品の魅力を伝える画像しか目に入らない)。
関連製品を購入するユーザーの多くは、既にその製品を知っているリピーターでした。そのため、製品の詳しい説明(商品概要)よりも、目的の製品にすぐにたどり着けるレイアウトの方が、ユーザーの手間を省き、利便性が高かったと推測されています。新しくなった製品についての情報よりも、ユーザーが求めていたのは「目的の商品への速やかなアクセス」であったことが判明しました。
バナーのABテスト事例
Sonyでは、製品紹介バナーのクリック率や購入数が伸び悩んでいました。特に、パソコンのカスタマイズや割引キャンペーンを同時に訴求するバナーが成果を出せていなかったのです。オンライン販売の改善を図るため、どの訴求が最も効果的かを見極める目的でABテストを実施しました。
| 【テストの目的】 バナー広告からのコンバージョン率を向上させること。 【仮説】 バナー広告に二つの異なる「行動を促すメッセージ」(カスタマイズ可能なノートパソコンの宣伝と、メモリー無料アップグレードのキャンペーン)が含まれていることが、顧客の混乱を招き、クリック率を下げているのではないか。 【テスト内容】 バナーの内容を変更し、以下の3パターンを比較。
【結果】 最も良好な結果を出したのは、カスタマイズ訴求に絞ったバリエーション1。クリック率は6%向上し、カート到達数は21.3%も増加しています。一方、キャンペーンのみを伝えたバナー(バリエーション2)は、クリック数はわずか1.8%の増加にとどまり、カート到達数はむしろ減少(2.9%マイナス)しました。 |
テスト後、さらに細かくセグメントごとの結果を分析したところ、国ごとの違いは見られませんでした。どちらの国でもカスタマイズ訴求の方が効果的だったのです。ただし、デバイスによって結果は異なりました。モバイルユーザーでは、キャンペーン訴求の方が効果が高く、クリック数が21%増加。これは、スマートフォン利用者には簡潔でお得感のあるメッセージの方が刺さる可能性を示しています。
CTAボタンのABテスト事例
ウェブサイト上での顧客獲得において、CTA(行動喚起)ボタンは非常に重要な役割を担います。ここでは、auフィナンシャルサービスの事例を参考に、CTAボタンのABテストによってコンバージョン率が向上した具体的な取り組みを紹介します。
クレジットカードの申し込みは、ユーザーにとって手間がかかる、面倒な作業と感じられがちです。「今使っているカードで十分」と考えているユーザーの行動を促すには、申し込みの強力な理由を提示する必要があります。そこで、「申し込むと何が得られるか」というメリットをCTAボタンの文言に含めることで、迷っているユーザーの背中を押し、クリック率が向上するという仮説が立てられました。
| 【テストの目的】 ランディングページ(LP)におけるコンバージョン率の改善。 ※過去のテストでは、文字数の少ないシンプルなボタンが効果的だった。しかし、今回のテストでは、特典をはっきり書くことの有効性を検証する目的も含まれている。 【仮説】 「申し込むと何が得られるか」というメリットをCTAボタンの文言に含めることで、迷っているユーザーの背中を押し、クリック率が向上するのではないか。 【テスト内容】 LP上のCTAボタンを変更し、以下の2パターンを比較。
【結果】 CTAボタンのABテストでは、Bパターンがクリック率でAパターンを上回る結果となりました。 |
この結果は、ユーザーが申し込みを検討する際に、具体的なメリット提示が有効であることを示しています。CTAボタンの文言に具体的なメリット(例:「最大10,000ポイントもらえる」)を含めることで、ユーザーの行動を促す強力な動機付けとなることが示されました。ユーザーは、その行動によって何が得られるのかを明確に知りたいと考えているため、メリットを直接的に伝えるほうが効果が高かったと推測されます。
参考記事:ボタン、メインビジュアル、利用イメージの多変量解析でCVR119%改善!〜auフィナンシャルサービスのABテスト事例
【有料】ABテストに役立つツール3選
ABテストの実施、分析、そしてウェブサイト全体の改善に役立つおすすめの有料ツールを3つご紹介します。
SiTest

SiTestは、アジア圏で広く使われているLPO(ランディングページ最適化)ツールです。ABテストだけでなく、ヒートマップ分析やエントリーフォーム最適化など、多くの機能を利用できます。
特に注目すべきは、HTMLやJavaScriptの専門知識がなくても、テキストやビジュアルの変更を簡単に行える点です。専門的なスキルがない担当者でも、スピーディーにABテストを進められます。レポート機能やパーソナライズ機能も充実しており、多角的な分析とユーザーへの個別最適化が可能です。
参照元:SiTest公式サイト
KAIZEN PLATFORM(KAIZEN UX)

KAIZEN UXは、Kaizen Platformが提供するウェブサイト改善サービスです。このツールの大きな特徴は、「KAIZEN TEAM」という伴走型のサポート体制です。ABテストの設計からデザイン作成、効果測定までを一貫してサポートしてくれるため、自社にABテストの知識やリソースがなくても安心して利用できます。
膨大なABテストの結果から得られたノウハウで課題解決をサポートしてくれるため、初めてABテストに取り組む企業にとって、ノウハウ不足を解消しながら効率的に改善活動を進められる点が大きなメリットです。
参照元:KAIZEN UX公式サイト
ミエルカヒートマップ

ミエルカヒートマップは、ヒートマップ分析やノーコードポップアップ機能を備えた国産のアクセス解析ツールです。直感的な操作性で、ユーザーの行動を視覚的に把握できます。
このツールでは、ノーコードでABテスト(同一URLテスト)を実施でき、テスト結果はリアルタイムで確認できます。効果の高いパターンを素早く把握できるため、次の施策に役立てられます。リダイレクトテストやパーソナライズ設定機能も搭載されており、より詳細なテストが行えます。無料お試し期間も用意されているため、本格導入前に試せるのもポイント。AIによるヒートマップ自動解析機能もあり、分析の手間を減らせるでしょう。
参照元:ミエルカヒートマップ公式サイト
【無料】ABテストに役立つツール2選
コストを抑えてABテストを始めたい企業にとって、無料で利用できるツールは大きな助けとなります。ここでは、無料でABテストを実施できるおすすめのツールを2つご紹介します。
Juicer
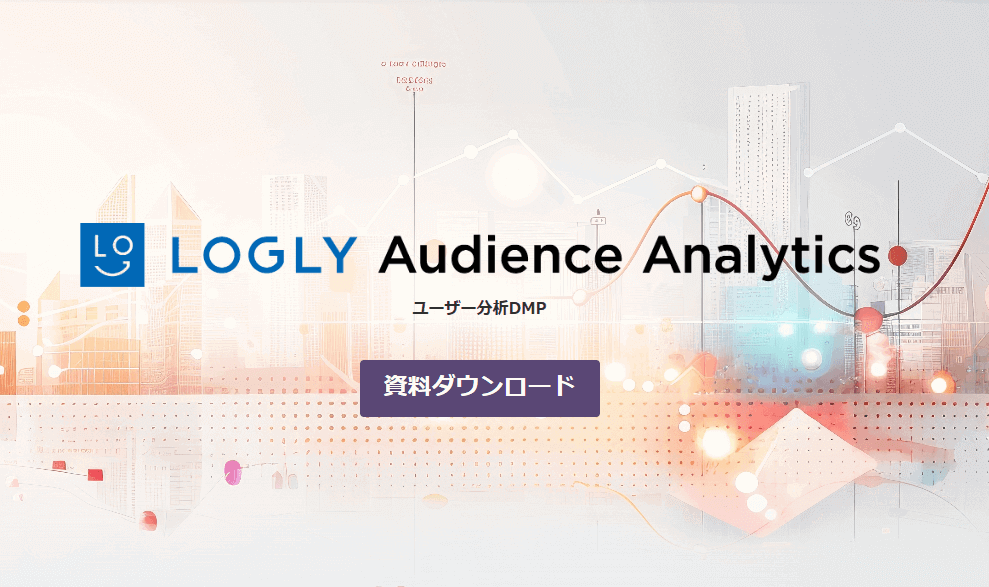
Juicerは、ABテストの手順を簡単に実行できる無料ツールです。テストしたいページの選択から、成果目標の設定まで、直感的な操作で進められます。
このツールはABテスト機能に加え、ペルソナ分析やアクセスログ解析といった機能も無料で提供しています。これにより、ユーザーの行動や属性を深く理解しながら、テストの効果を最大化できるでしょう。無料の基本プランに加え、さらに高度な機能を利用できる有料オプションも用意されています。
参照元:Juicer公式サイト
OptimizeNext
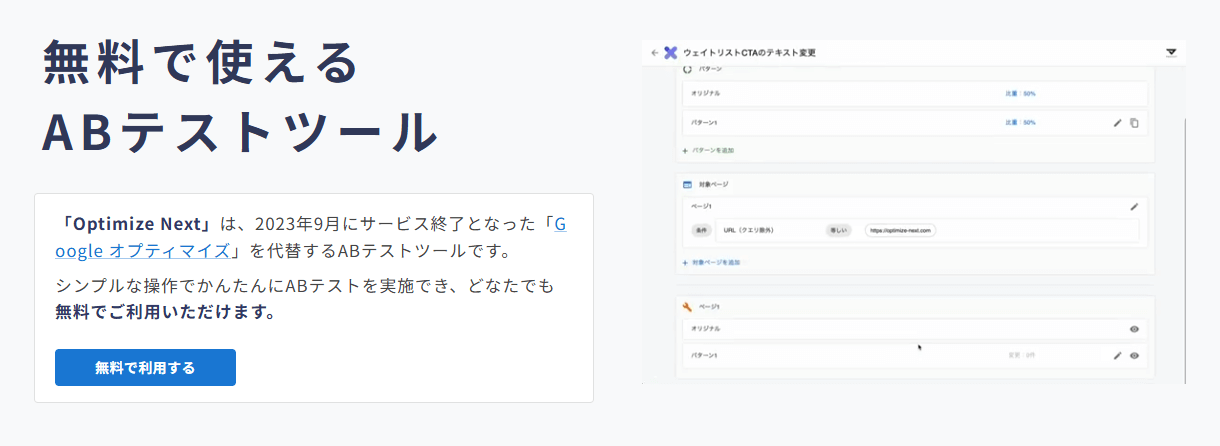
OptimizeNextは、PROJECT GROUP株式会社が開発した無料のABテストツールです。Google Optimizeの終了後、その後継ツールとして誕生しました。
このツールの特徴は、直感的で使いやすい操作画面と、日本語への対応です。2025年3月時点で、すでに4,600以上のウェブサイトに導入されており、多くの企業で利用されています。基本的なABテスト機能は無料で利用できますが、施策管理機能を備えた有料プランも提供されており、ビジネスの規模やニーズに合わせて選択可能です。
まとめ
ABテストは、ウェブサイトや広告の効果を科学的に検証し、データに基づいた改善を繰り返すための手法です。単なる比較にとどまらず、ユーザーの行動や心理を深く理解し、仮説検証のサイクルを回すことで、より本質的な改善へとつながります。
紹介した事例のように、バナーの文言一つ、CTAボタンの色一つで、コンバージョン率が大きく変わることも珍しくありません。SiTestやKAIZEN PLATFORM、ミエルカヒートマップのような有料ツールから、JuicerやOptimizeNextといった無料ツールまで、さまざまな選択肢があります。自社のリソースや目的に合わせて、効率的にABテストを進めましょう。
ABテストは一度行えば終わりではありません。常に変化する市場やユーザーのニーズに対応するためには、継続的な実施が大切です。本記事で得た知識を活かし、ぜひABテストを実践してみてください。成果につながる施策を積み重ね、ビジネスの成長を加速させましょう。
『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする
以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本
監修者
クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。
営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。