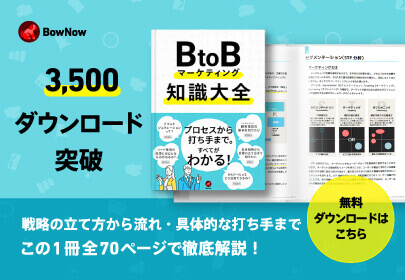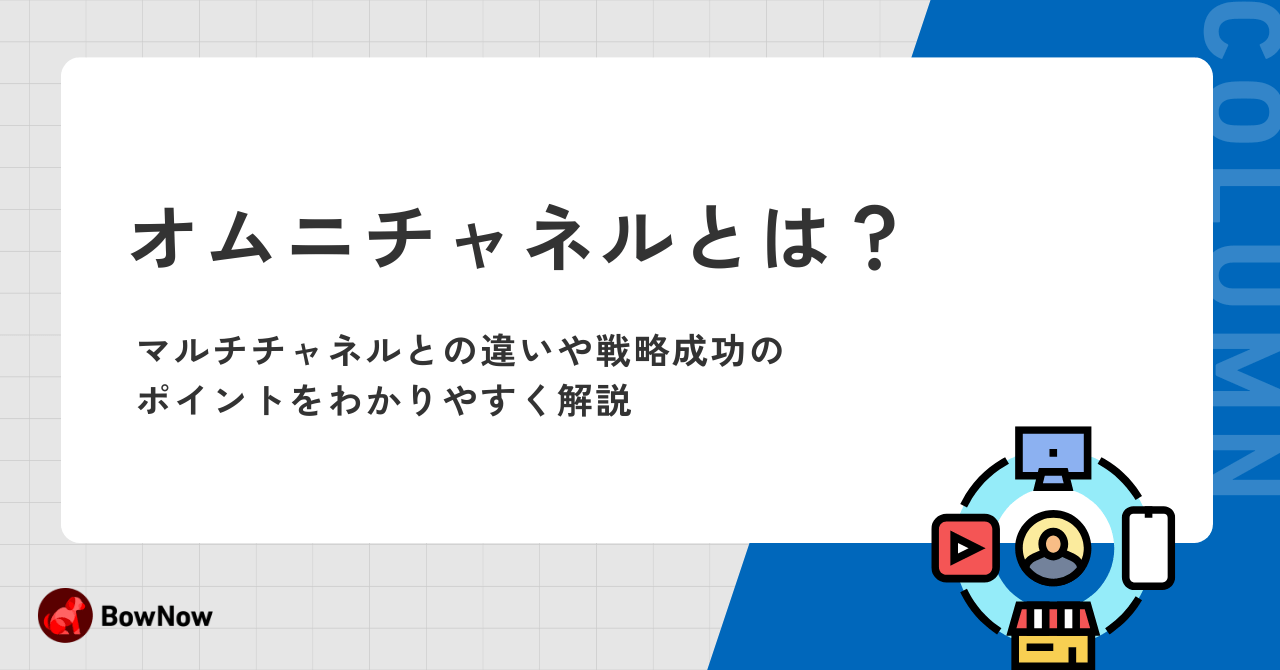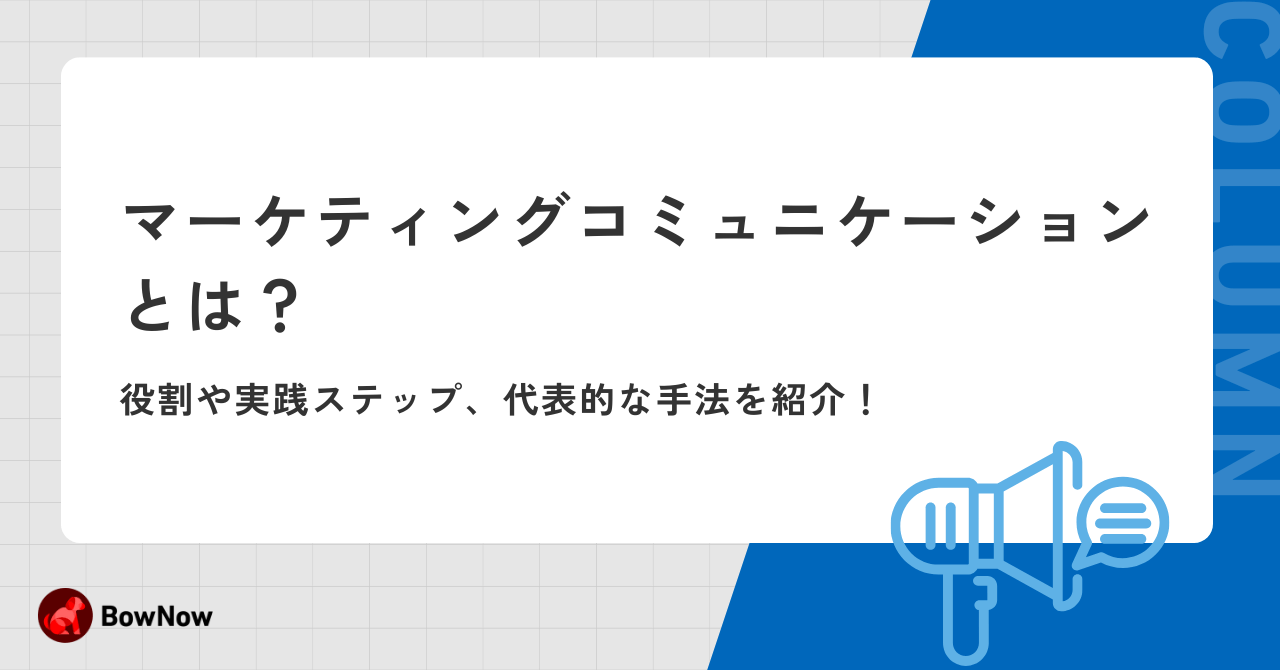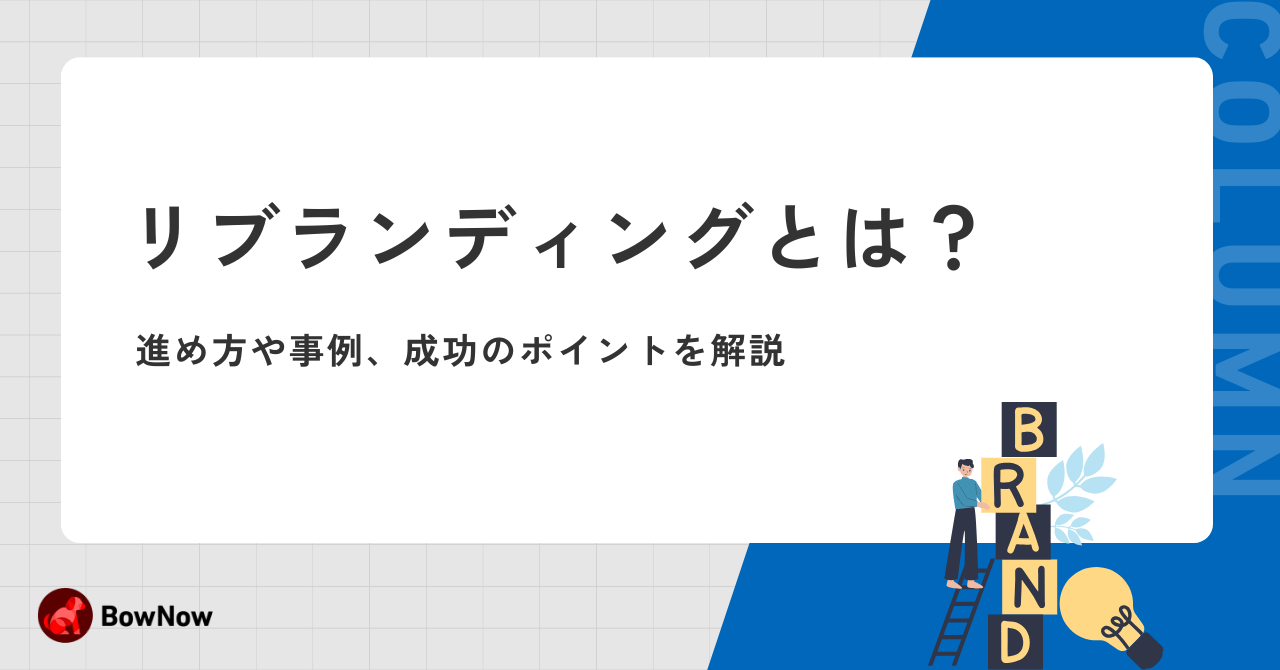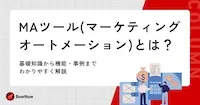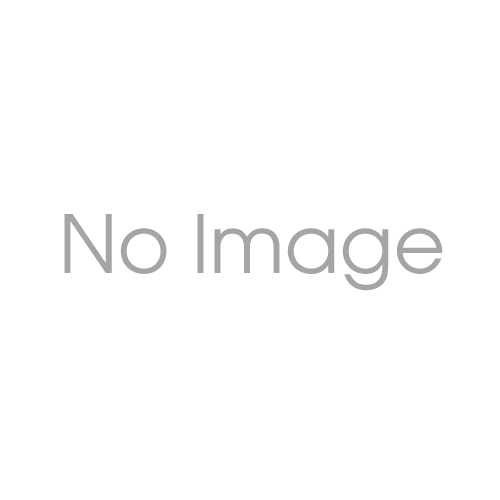ブランディングとは?目的・種類・進め方・事例までわかりやすく解説
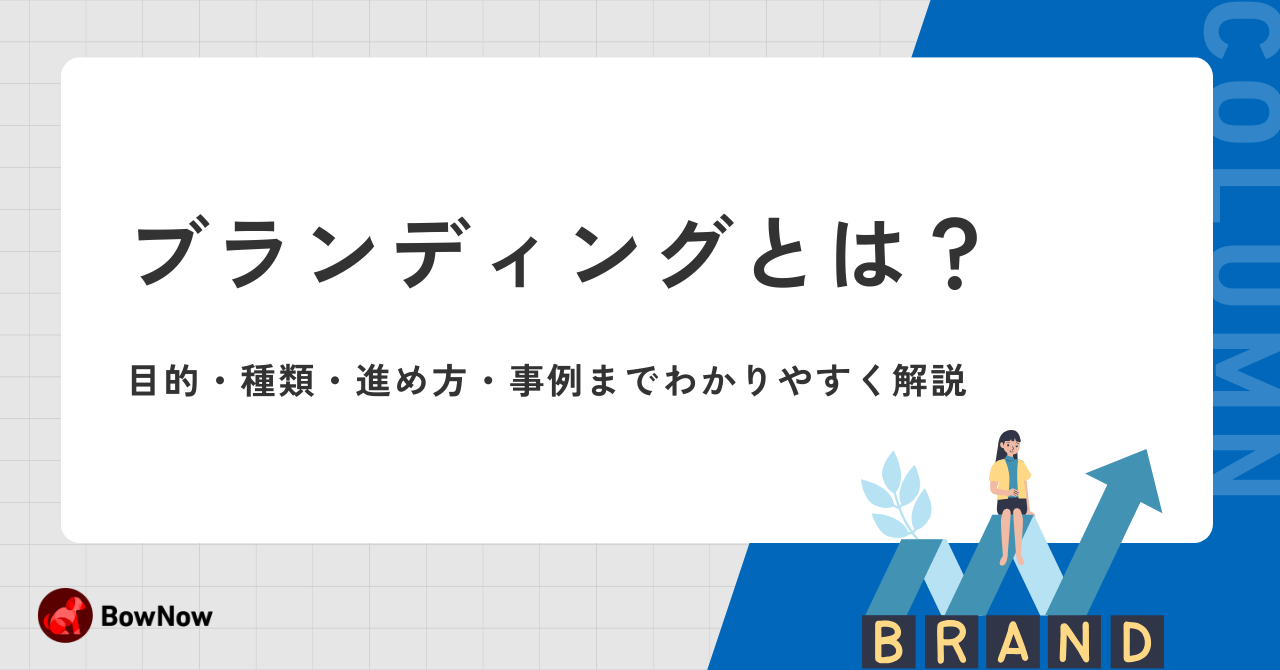
ブランディングは、企業や商品が持つ独自の価値や印象を明確にし、顧客に伝えていく取り組みです。商品やサービスがあふれる中で、単に「質が良い」だけでは選ばれない時代になりました。そこで注目されているのが「ブランディング」です。この記事では、ブランディングの意味や必要とされる背景、他のマーケティング手法との違いまで、わかりやすく解説していきます。
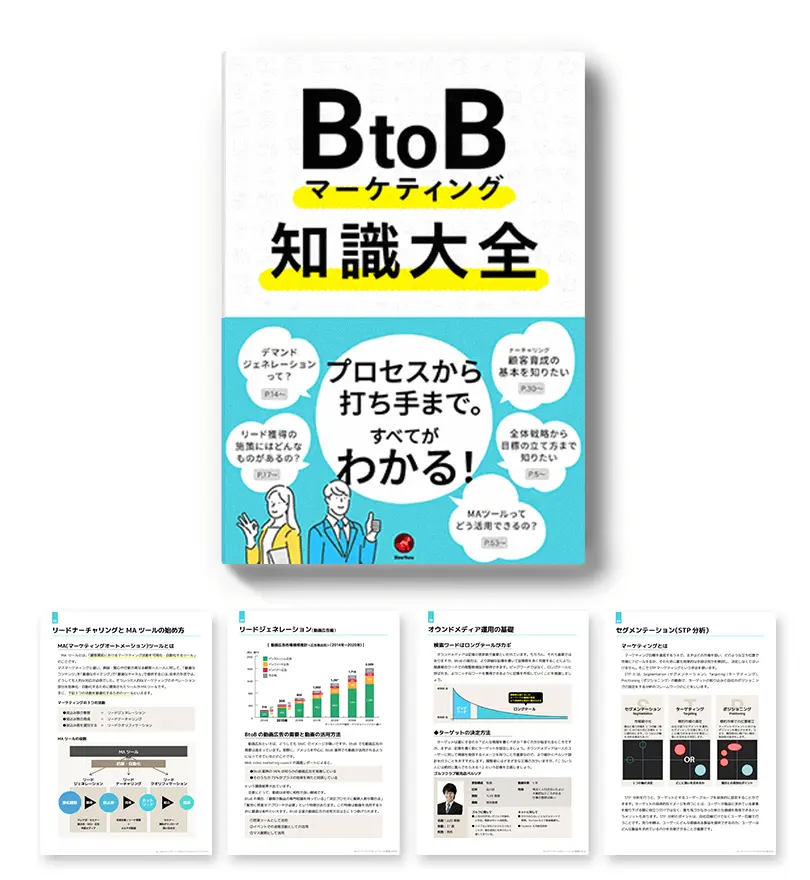
3,500ダウンロード突破!
『BtoBマーケティング知識大全』
BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。
まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。
目次
ブランディングとは?
ブランディングとは、企業や製品、サービスが持つ独自の価値や個性を顧客に明確に伝え、他社にはない独自の存在感をつくる活動です。単に製品を販売するだけでなく、顧客の心に深く響くイメージや信頼を構築し、選ばれ続ける関係性を目指します。
ブランディングの定義
ブランディングは、社名やロゴ、サービス内容にとどまらず、広告や営業の対応など、あらゆる接点を通じて「選ばれる理由」をつくり出します。単なる見た目の統一ではなく、「この会社はこういう価値を提供している」と市場に理解してもらうことが“ブランディング”です。そのため、短期的な売上よりも、長期的な信頼やブランド認知の蓄積が重視されます。
ブランド=高級品という誤解
ブランドと聞くと「高価」「贅沢」なイメージを持つ人もいますが、必ずしもそうではありません。ブランドとは、商品や企業に対して感じる印象や価値のことです。たとえば、ある外食チェーンが「早くて手ごろ」「家族でも気軽に行ける」といったイメージを確立していれば、それも立派なブランドです。価格の高低は関係なく、「他とは違う価値がある」と認識されることがブランドの本質です。
ブランドを形づくる代表的な要素
ブランドは複数の要素が組み合わさって成り立っています。代表的な要素は次の通りです。
|
【視覚・構造面の要素】
|
これらは、企業や製品の第一印象を左右する要素であり、顧客に「どんなブランドか」を直感的に伝えるために欠かせません。さらに以下もブランドを構成する大切な要素です。
|
【価値・体験に関する要素】
|
これらの要素が整っていることで、顧客の記憶に残るブランドとなり、他社との差別化や競争力の向上へとつながります。
ブランディングが求められる背景
ブランディングが必要とされる理由は、主に3つあります。
|
まず、市場競争が激しくなり、類似した商品やサービスが増えている点が挙げられます。企業は、多くの商品の中から「自社を選んでもらう理由」を明確に示す必要が出てきました。その一環としてブランディング活動が重視されています。次に、顧客の信頼を獲得することの重要性が高まっていることです。ブランディングにより企業の理念やこだわりを伝えることで、顧客との心理的なつながりが深まり、顧客からの信頼獲得・長期的な関係構築が可能になります。
最後に、ブランドが確立されると、商品やサービスだけでなく、背景にある価値やストーリーも評価されます。これは、高い利益率の維持や優秀な人材の獲得、企業全体の価値向上につながります。ブランディングは単なる見た目の変更ではなく、市場で競争に勝ち抜き、長く成長していくための戦略的な活動として注目されています。
ブランディングとマーケティング・プロモーションの違い
ブランディング、マーケティング、プロモーションは、企業が市場で成功するために連携して行われる活動ですが、それぞれ異なる目的と役割を持っています。
| ブランディング | 長期的に顧客との関係を築き、 企業や商品に対する信頼や好感を育てる活動です。 |
|---|---|
|
マーケティング |
顧客のニーズを調査し、商品やサービスを市場に届けるための活動全般を指します。どのような手段で販売するかが主な関心事です。 |
|
プロモーション |
商品の販売を促すための短期的な施策です。割引や広告、キャンペーンなどが該当します。 |
3つの活動は独立しているのではなく、互いに補完し合う関係にあります。ブランディングによって築かれた信頼基盤の上で、マーケティングやプロモーションがより効果的に機能し、相乗効果を生み出します。
ブランディングの分類
目的や対象に応じて、いくつかの分類が存在します。ここでは代表的な以下5つのブランディングの種類について紹介します。
|
インナーブランディング
インナーブランディングは、社内に向けたブランディング活動です。企業の理念や価値観を従業員に伝え、共通認識を育てます。具体的には、社内報やイベント、社内SNS、従業員向けのイベントなどを使い、企業文化を根付かせる取り組みが行われます。従業員が自社ブランドを理解し、行動に移すことで、組織全体の一体感が高まり、顧客への高品質なサービス提供にもつながります。
商品・サービスブランディング
商品やサービスの認知度や信頼感を高めるためのブランディングです。商品そのものの魅力や独自性を明確に打ち出し、消費者に選ばれる理由を作ります。たとえば、ウェブサイトや動画、SNSで商品特性を伝えるとともに、パンフレットや展示会などのオフライン施策を組み合わせて展開します。BtoB分野では、導入事例や課題解決のストーリーなど、実績を通じた訴求が効果的です。
コーポレートブランディング
企業全体のイメージや信頼性を高めることを目的としたブランディングです。製品やサービスだけでなく、企業全体の信頼性、革新性、社会貢献性などを社会や取引先に伝えることで、企業の価値向上を目指します。ロゴや社名、公式サイトの刷新、社会貢献活動などが代表的な施策です。
採用・育成ブランディング
求職者や社員に向けて自社の魅力を発信するブランディングです。自社の文化や働きがい、成長の機会を伝えることで、優秀な人材の獲得と定着を図ります。採用サイトやSNS、説明会、社員インタビュー記事の掲載などが主な手段です。
インフルエンサーブランディング
影響力のある個人の発信を通じて、商品やサービス、企業の認知拡大を図る手法です。インフルエンサーブランディングは特にSNSでの情報拡散力が高く、インフルエンサーのファンに対してはより大きな効果が期待できます。ビジネス分野でも、専門家や業界リーダーの推薦が信頼獲得につながります。インフルエンサーの選定においては、自社の価値観と合致するかを見極めることが重要です。
ブランディングの主な目的・メリット
ブランディングとは、単に企業名やロゴを整えるだけの作業ではありません。自社の理念や価値を顧客や社会にわかりやすく伝えることで、選ばれる理由をつくる重要な取り組みです。ここでは、ブランディングによって得られる主な効果について説明します。
競合との差別化による市場優位の確保
自社の強みや特徴を明確に打ち出すことで、他社との差別化ができます。たとえば、製品の品質、サポート体制、環境への配慮など、価格以外の価値を伝えることで、顧客は「このブランドを選ぶ理由」を見いだせます。価格競争に巻き込まれることなく、独自の立ち位置を築けるため、安定した利益を確保しやすくなります。
顧客ロイヤルティとリピート率の向上
信頼されるブランドは、繰り返し選ばれる傾向があります。ブランドに対する信頼は、品質やサービスだけでなく、情報発信の一貫性や企業の姿勢によっても育まれます。「この会社なら安心して任せられる」と感じてもらえれば、自然とリピーターが増え、結果として、安定した売上と長期的な関係構築につながります。
新規顧客の獲得と市場の拡大
ブランド力のある企業は、口コミやSNSを通じて情報が広がりやすく、新たな顧客層にもアプローチしやすくなります。近年では、口コミやSNSなどのチャネルを通じて、情報が素早く広がる傾向にあります。信頼性のあるブランドとして認識されれば、既存市場にとどまらず、新しい分野や海外市場への展開も後押しされます。たとえば、既に評価されている企業が新規事業を立ち上げた場合、その信頼がそのまま新市場での優位性となります。
ブランディングの進め方を8ステップで解説
ブランディングは計画的に進めることで、最大の効果を発揮します。ここでは、効果的なブランディングを行うための以下8つのステップを順に説明します。
|
ステップ1:目指すブランド像を明確にする
まずは、自社がどんなブランドになりたいか、ブランドの方向性を定めます。市場や業界の動向、自社の強み、顧客のニーズ、競合の特徴を客観的に分析し、自社がどのような価値を提供すべきかを明らかにします。市場や競合を分析する3C分析、外部環境を調べるPEST分析などの手法を用いることで、より正確な方針が見えてきます。
ステップ2:社内でブランディングの重要性を共有
ブランディングは社外に向けた取り組みであると同時に、社内の協力が不可欠です。経営層から現場まで、すべての従業員がブランドの考え方や方向性を理解し、共通の意識を持つことが、統一感のあるブランド体験を提供する土台となります。
ステップ3:ブランドの基本コンセプトを固める
「誰に、どのような価値を届けるか」という問いに明確に答えるのが、ブランドコンセプトです。顧客の課題や期待に寄り添い、それに応える形でブランドの中心となる価値を定めます。明確なコンセプトは、営業や広告などあらゆる活動の軸になります。
ステップ4:ブランドの核となるイメージを構築
ブランドの印象を形づくる要素には、ロゴやキャッチコピー、配色、デザインなどがあります。これらに統一感を持たせて設計することで、ブランドの個性を一貫して伝えることができ、ブランドのイメージを強く印象付けられます。視覚的な印象だけでなく、言葉や態度も含めた全体像を設計することが重要です。
ステップ5:ブランドが提供する価値を定義
ブランドの価値とは、顧客がそのブランドを選ぶ理由のことです。機能的な価値(品質や性能)、感性的な価値(デザインや雰囲気)、情緒的な価値(使用時の満足感)、共感価値(社会貢献や価値観の共有)などがあります。これらを明確にすることで、顧客から長く愛されるブランド作りが行えます。
ステップ6:ブランド名やロゴを具体化
ブランドを象徴する名前やロゴは、直感的にブランドの特徴を伝える重要な要素です。覚えやすく、独自性があり、かつブランドの価値や世界観を感じさせる名称やデザインが求められます。実際に使われる場面を想定しながら作成することがポイントです。
ステップ7:顧客接点ごとのブランド体験を設計
ブランドとの接点(タッチポイント)とは、SNS、広告、営業資料、店舗の内装、接客対応など、顧客がブランドに触れるすべての場面を指します。顧客とのあらゆる接点で一貫したブランド体験を提供することが重要です。どのような体験を提供していくのかを考えます。
ステップ8:定期的に施策の効果と認知度を確認
ステップ7が終わったら、いよいよブランディングの実施に入ります。ブランディングは長期的な施策です。ただ一度実施しただけでは高い効果が見込めません。定期的に調査や分析を行い、認知度や顧客の印象を確認し、必要に応じて戦略を見直します。継続的な改善を重ねることで、ブランドの価値をさらに高めていくことができます。
効果を高めるために意識するポイント・注意点
効果を高めるために押さえておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
一貫性のあるブランドコミュニケーション
ブランドの価値を伝えるには、一貫性のある情報発信が欠かせません。企業のロゴや色づかい、キャッチコピーなど、視覚的・言語的な要素を統一することで、顧客に安心感や強い印象を与えられます。
広告やSNS、営業資料、店舗の内装など、すべての顧客接点において同じ価値観やメッセージを伝えることが大切です。情報の内容や見せ方にばらつきがあると、顧客の混乱を招き、ブランドへの信頼が揺らぐおそれがあります。ブランディングでは、ブランドが何を大切にしているのか、その方向性を明確にして、すべての発信内容に反映させるよう意識することが重要です。
顧客とのエンゲージメントの強化
ブランディングは一方的な発信だけでなく、顧客とのつながりづくりも重要です。商品やサービスを通じて顧客と信頼関係を築くことが、ブランドへの愛着を育てる第一歩になります。
具体的には、SNSでの対話、アンケートによる意見収集、イベントでの交流などがあります。これらを通じて顧客の声を取り入れながら、ブランドが成長していく過程を共有することで、顧客は「参加している」感覚や愛着を持ちやすくなります。エンゲージメントが高まれば、顧客の満足度やロイヤルティも向上し、長期的な関係構築につながります。
競合との差別化
市場での存在感を高めるには、自社ならではの強みを明確にし、それをブランドに反映させる必要があります。たとえば技術力、サポート体制、持続可能性への取り組みなど、他社にはない価値を伝えることで、顧客が自社を選ぶ理由が生まれます。
そのためには、競合の特徴や顧客のニーズをしっかり把握した上で、自社の立ち位置を定めることが重要です。ただし、差別化のために奇抜な要素を取り入れるのではなく、顧客視点での納得感ある独自性が求められます。また、ブランドコンセプトを言葉にして発信することも重要です。曖昧なままでは伝わらず、顧客の判断材料になりません。明文化し、社内外にしっかり届けましょう。
ブランディングの事例3選
ブランディングの事例を3つ紹介します。
企業ブランディングの事例:無印良品
無印良品は、「必要なものを、必要なだけ」をコンセプトに、1980年に誕生しました。その考えの通り、シンプルで無駄を省いた製品づくりが特徴です。製造工程や素材選びを見直し、本当に必要な要素だけを残しています。この姿勢が、「引き算の美学」として、現在もブランドの核になっています。
製品だけでなく、店舗やパッケージにもコンセプトが一貫しています。白を基調とした空間設計や、最小限の情報だけを載せたパッケージにより、「誠実さ」や「信頼感」を表現。さらに、再生素材の活用や地域との協働など、持続可能性を重視した取り組みも進めています。「Found MUJI」では世界の暮らしを尊重した商品開発を行い、グローバル市場でも共感を得ています。
ブランド立ち上げ当初から「コンセプトづくり」に力を注ぎ、消費者に寄り添いながらも、自社の芯を守り続ける姿勢が、無印良品の強みです。
インナーブランディングの事例:セブンデックス
セブンデックスは、理念が現場に浸透しないという課題に直面し、理念を組織に定着させるための取り組みを強化しました。当初、半年かけて策定した理念は完成度が高いものでしたが、現場からは「どう行動に結びつけたら良いのか分からない」という声が出ました。その背景には以下の3点がありました。
|
この課題を受けて、理念の「翻訳」と「体現」に注力しました。具体的には、全社ワークショップを実施し、理念を自分の言葉で語る練習や、業務との接点を話し合う場を設けました。さらに、部門ごとに「自分たちなりの理念の実践」を明文化することで、理解を行動につなげる工夫も行いました。加えて、朝会での好事例共有や1on1での対話、表彰制度などを通じて、理念が自然と浸透する環境づくりを進めました。
この結果、採用時に理念への共感を示す応募者が増えたほか、社員の行動の質も向上。現場からの自発的な提案も増え、組織全体の一体感が高まっています。
商品ブランディングの事例:ブラックサンダー
ブラックサンダーは、有楽製菓が長年かけて築いたブランドです。競合の多い菓子市場で売上が鈍化したため、25周年を機にブランドの価値を再整理し、社内の共通理解とブランドの一貫性を強化しました。
社内外でブランドイメージにばらつきがあったことから、ロゴの見直しやブランドガイドラインを作成。社員が集まり何度も話し合うワークショップを実施し、ブランドが持つ独自の価値や性格を具体的な言葉として整理し、全社員で共通の理解を作りました。これにより、商品企画やプロモーションの方針が統一され、ブランディングのぶれを防ぐ基盤ができました。
また、「楽しく真剣にやる!」をテーマに、独自のマーケティング施策を展開。たとえば、義理チョコ文化が薄れていた中、ブラックサンダーは「義理チョコの素」というセット商品や、義理チョコ専用のショップを展開しました。ブランドの個性を活かしつつ、義理チョコを楽しく贈る新しい価値を提案し、新たな顧客層の獲得に成功しました。こうした戦略でブラックサンダーは、単なる菓子を超えた「面白くて身近なブランド」として成長を続けています。
参考記事:ブラックサンダー 商品ブランディング事例
ブランディングの知識を深めるには?
ブランディングを学ぶ主な手段は以下の通りです。
|
ブランディングをしっかり学ぶには、まず関連書籍を読むのがおすすめです。専門書では基礎理論や実践例が分かりやすく解説されており、自社に活かせるアイデアを得られます。忙しい方は、オンライン講座も便利です。動画で視覚的に理解でき、マーケティングやデザインの関連知識も同時に学べます。月額制サービスなら幅広くスキルを身につけられます。
さらに本格的に学びたい場合は、専門学校や大学の授業が適しています。業界の専門家から直接指導を受けられ、最新の知識を習得できます。また、ワークショップやセミナーに参加することで、実務経験に基づくアドバイスや多様な視点を取り入れられます。オンライン開催も多く、参加しやすいのも特徴です。
理論だけでなく、実際に自分でブランディングを試みることも重要です。小規模なプロジェクトから始め、経験を積むことでスキルが高まります。実践を通じて得た知見は、今後の活動に大きく役立つでしょう。
まとめ
ブランディングは、単なる認知拡大ではなく、価値や信頼を育てる継続的な取り組みです。自社の特徴を正しく伝え、顧客との関係を深めるために、一貫した情報発信や体験の提供が求められます。本記事の内容や事例なども参考に、自社のブランディング戦略を具体化してみてください。
『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする
以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本
監修者
クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。
営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。