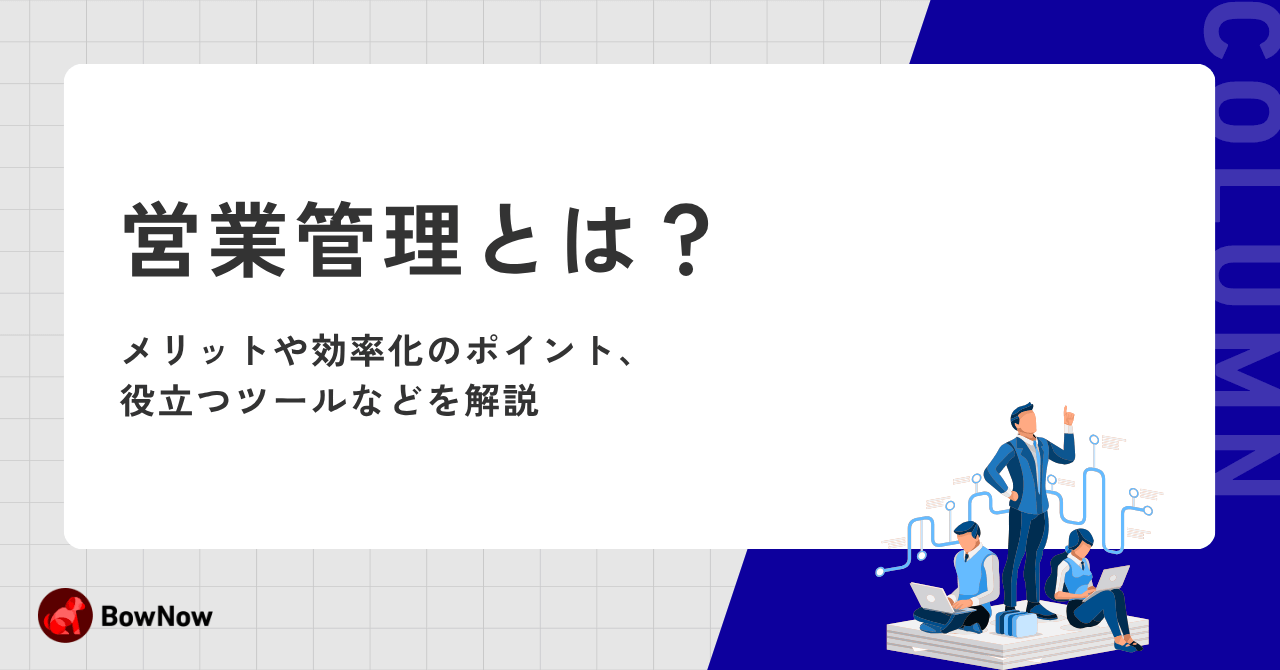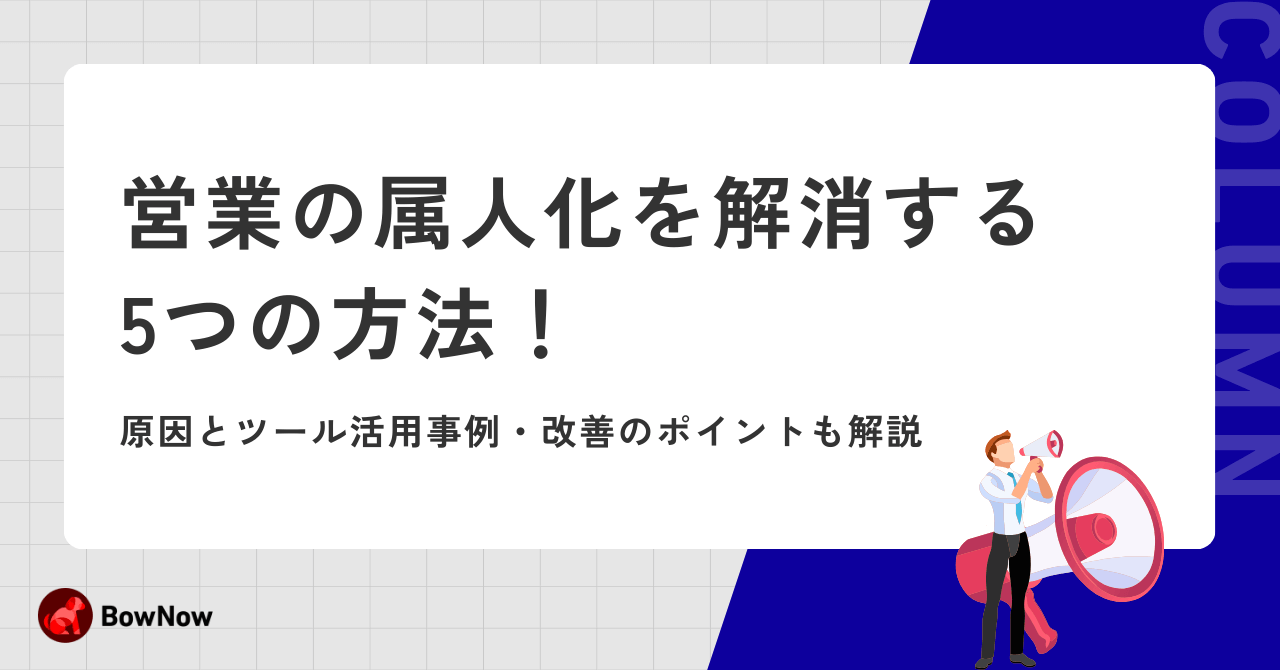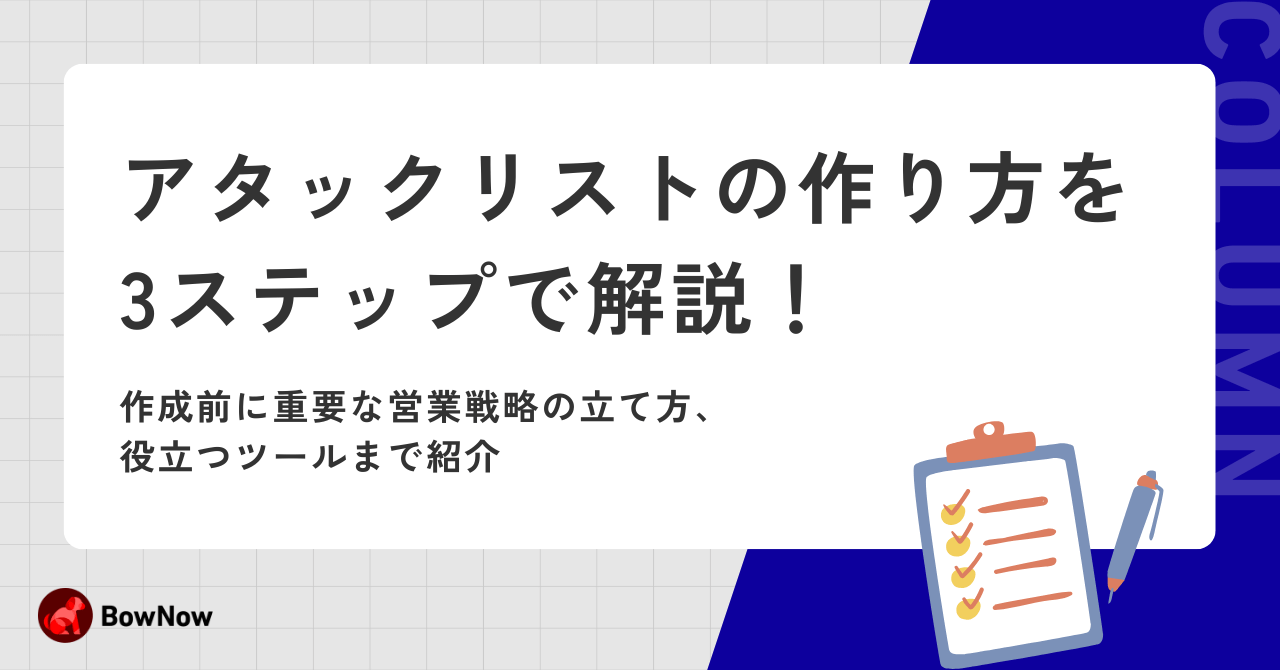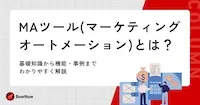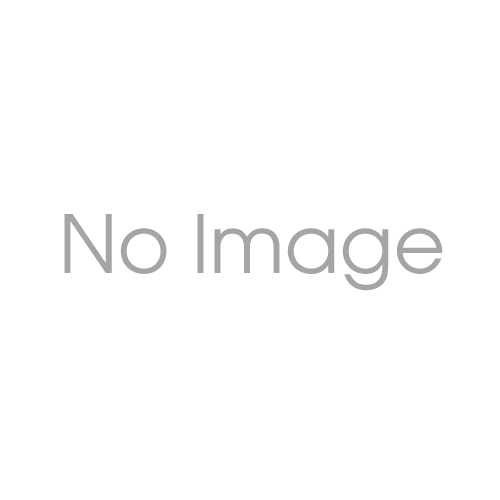オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンとは?商談をスムーズに進める活用術を解説
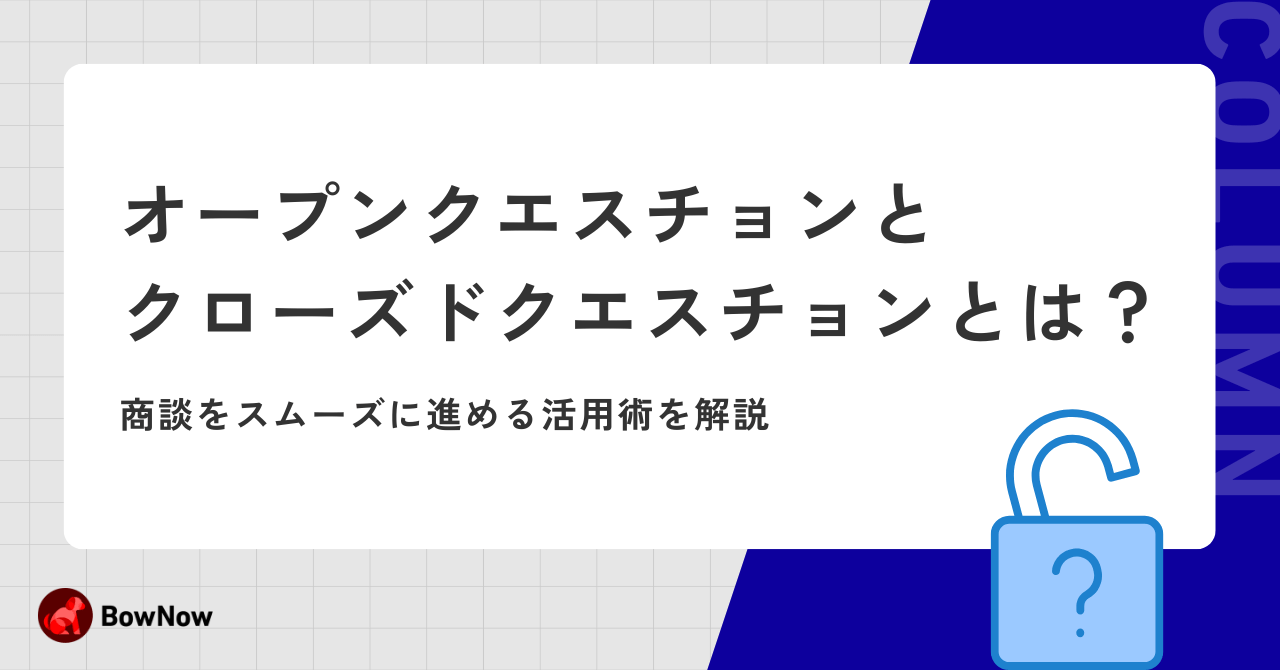
商談や顧客ヒアリングの成果は、「質問力」で大きく変わります。そのなかでも注目したいのが、「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」という2種類の質問形式です。オープンクエスチョンは、相手が「はい」「いいえ」では答えられず、自由に意見を話してもらう質問形式です。一方で、クローズドクエスチョンは「はい」「いいえ」や、複数の選択肢から答えてもらう形です。
ビジネスシーンでは、この2つを状況に応じて使い分けることが求められます。本記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリット、活用のコツを解説します。
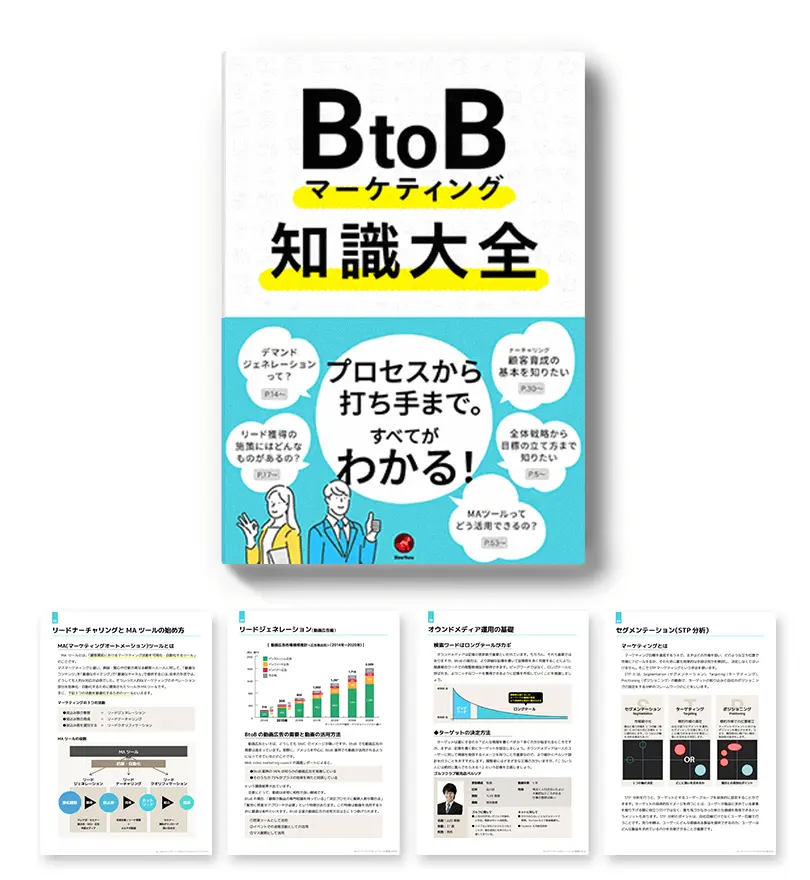
3,500ダウンロード突破!
『BtoBマーケティング知識大全』
BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。
まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。
目次
オープンクエスチョンとは
オープンクエスチョンとは、相手に自由に答えてもらう質問のことです。たとえば、「今回の打ち合わせで重視している点はどこですか?」「今後の取り組みで大切にしたいことは何ですか?」といった聞き方です。答え方に幅があるため、相手の考えや価値観を深く理解できます。
ただし、あまりに漠然とした聞き方は答えにくさにつながります。そこで「5W1H(いつ・どこ・だれ・なに・なぜ・どうやって)」を意識して、答えやすい範囲を示すと会話がスムーズです。オープンクエスチョンを取り入れることで、商談の質が上がり、信頼関係の構築にもつながります。
オープンクエスチョンのメリット
オープンクエスチョンを活用すると、次のような効果が期待できます。
考えや気持ちを自由に話してもらえる
最大の特徴は、相手が自分の意見を自由に話せる点です。「どのように感じましたか?」「今後どのように進めたいですか?」と聞けば、相手は自然と考えを言葉にしやすくなります。「はい」「いいえ」で答えを限定しないため、回答者は自分の言葉で、自分のペースで考えや気持ちを表現できます。その結果、相手は「自分の話をしっかりと聞いてもらえている」と感じ、安心感を抱きやすくなるでしょう。
商談の場で自由に話せる空気をつくれば、相手との距離が縮まり、会話もスムーズに進みます。相手に気持ちよく話してもらうための環境づくりや、信頼関係を築くうえでとても大切な役割を果たします。
多くの情報を引き出せる
相手が自由に話せるということは、質問者側から見ると「より多くの、そして質の高い情報を引き出せる」という大きなメリットにつながります。
たとえば、「このサービスを利用するうえで、不安に感じる部分はどこですか?」と尋ねれば、具体的な課題や期待している効果まで聞き出せる可能性があります。想定していなかった意見が出てくる場合もあるため、商談やヒアリングをより有効に進められます。
さらに、相手の答えをもとに追加で質問を投げかければ、会話を自然に深掘りできます。相手の優先事項や本音を理解できる点は、オープンクエスチョンの大きな魅力といえるでしょう。
オープンクエスチョンのデメリット
一方で、オープンクエスチョンには注意点もあります。代表的なものを3つ見ていきましょう。
回答に時間がかかる
自由に答えられる分、相手は考えを整理する必要があります。「どのように感じていますか?」「今後の課題は何ですか?」といった質問は、回答に時間がかかり、心理的な負担になることもあります。初対面や信頼関係が築けていない場面では、緊張して答えづらいケースもあるでしょう。相手に考える余裕を与える配慮が大切です。
ヒアリングが長引く可能性がある
会話の幅を広げやすい反面、ヒアリングに時間がかかりすぎることがあります。自由に話せるため、相手が話を広げすぎたり、想定外の方向へ進んだりすることも少なくありません。その結果、商談や打ち合わせの予定を超えてしまう場合もあります。
情報を多く得られるのはメリットですが、時間が限られているとデメリットになり得ます。事前に目的を共有し、必要に応じてクローズドクエスチョンを組み合わせる工夫が効果的です。
本音を聞き出すには信頼関係が必要
オープンクエスチョンは、関係性によって答えの質が変わります。たとえば「現状の課題は何ですか?」と尋ねても、信頼関係ができていなければ無難な答えしか返ってこないこともあります。
逆に、安心して話せる環境があれば、本音を引き出せる可能性が高まります。商談やヒアリングでは、いきなり核心に迫るのではなく、段階的に話を進めるようにしましょう。信頼を築いていくことで、相手も率直に意見を話しやすくなります。
オープンクエスチョンの活用シーン
オープンクエスチョンは、「ニーズを把握したいとき」「場の雰囲気を和ませたいとき」に効果を発揮します。質問例とあわせて解説します。
ニーズを把握したいとき
商談では、製品やサービスに対する期待だけでなく、導入後の運用イメージや社内で感じている課題まで把握する必要があります。オープンクエスチョンを活用すれば、顧客が本当に求めているものを知ることができ、次の提案につなげやすくなります。
【質問例】
|
場の雰囲気を和ませたいとき
初対面の商談や緊張感のある場面では、いきなり本題に入るよりも、オープンクエスチョンで会話をはじめるほうが自然です。軽い話題を投げかけることで距離が縮まり、相手もリラックスして本音を話しやすくなります。
特に商談の導入部分では、相手が答えやすい質問を準備しておくと、その後の会話がスムーズに進みやすくなるでしょう。
【質問例】
|

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』
この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本
クローズドクエスチョンとは
クローズドクエスチョンとは、答えを限定する質問方法です。自由に答えてもらうオープンクエスチョンとは対照的に、「はい」「いいえ」や、こちらが用意した選択肢の中から答えてもらう形になります。
たとえば、「現在このサービスを利用していますか?」という質問は「はい・いいえ」で答えられます。また、「お打ち合わせの日程は、来週と再来週ではどちらがご都合よろしいですか」と具体的な選択肢を示すのもクローズドクエスチョンの一例です。相手が答えに迷うことが少ないため、会話をテンポよく進めたいときや、相手の意思を明確に確認したい場面で役立ちます。
クローズドクエスチョンのメリット
クローズドクエスチョンには、主に次の3つのメリットがあります。
回答者がスムーズに答えやすい
クローズドクエスチョンは「はい・いいえ」で答えられるため、相手にとって負担が少ない質問になります。いきなりオープンクエスチョンで答えを求めると、「何から話そうか…」と相手が戸惑うこともありますが、シンプルに答えられる質問なら自然に会話をはじめられます。
会話をテンポよく進められる
短時間で答えが得られるのもクローズドクエスチョンの強みです。回答がシンプルなため、やりとりが滞りにくく、商談をスピーディーに進められます。限られた時間で効率的に話を進めたいときに役立ちます。
また、相手の状況を確認したり条件を絞り込んだりするときにも有効です。会話がテンポよく進めば、相手の集中力も保ちやすく、全体の流れがスムーズになります。
主導権を握って相手の決断を促せる
クローズドクエスチョンは、こちらが用意した選択肢の中から答えてもらう形式なので、会話の流れをコントロールしやすくなります。
たとえば「導入時期は今期をお考えですか?」や「こちらとこちらなら、どちらを優先されますか?」と尋ねれば、相手に具体的な判断を促せます。商談を次のステップに進めたいとき、主導権を保ちながら意思を引き出せる点は大きなメリットです。
クローズドクエスチョンのデメリット
クローズドクエスチョンには、次のようなデメリットもあります。
問い詰められているような印象を与えやすい
クローズドクエスチョンは答えやすい反面、連続して使いすぎると相手に圧迫感を与えてしまいます。「はい・いいえ」で答える質問が続くと尋問のように感じられたり、自由に考えを話せないことが不信感につながったりすることもあります。商談では、オープンクエスチョンを混ぜながらバランスを取ることが大切です。
会話が途切れやすい
「質問→短い回答」で終わることが多いため、テンポよく進む一方で、会話が深まらず、単調になりやすいのがデメリットです。たとえば「この機能は必要ですか?」と尋ねて「はい」と返ってきた場合、そのまま会話が止まってしまうことがあります。
クローズドクエスチョンで得た答えをきっかけに「なぜそう思われたのですか?」など、オープンクエスチョンに切り替えると、会話の厚みが増していきます。
クローズドクエスチョンの活用シーン
ここからは、実際にクローズドクエスチョンが活躍する場面を見ていきましょう。
商談の導入時やクロージング
商談の始まりや終わりなど、重要な場面ではクローズドクエスチョンが効果を発揮します。会話のペースをつかみやすく、話したいテーマに沿って会話を進めやすくなります。
たとえば、商談の冒頭で「本日は〇〇についてお話しするのでよろしいでしょうか?」と確認すれば、お互いの認識を合わせてスムーズに本題に入れます。もちろん、オープンクエスチョンで自由に話してもらう時間も必要ですが、話が脱線したときにはクローズドクエスチョンで方向を修正すると効果的です。
さらにクロージングの場面では、クローズドクエスチョンが相手の決断を後押しします。「AプランとBプランならどちらが魅力的ですか?」と選択肢を示せば、具体的に検討しやすくなります。小さな「Yes」を積み重ね、契約へ自然につなげていくのが理想的な活用法です。
【質問例】
|

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』
この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの成功ポイント
両方の質問をバランスよく使うために、意識したいポイントをご紹介します。
会話のリズム・流れを意識する
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンは、あくまで会話を円滑にするための手法です。テクニックに気を取られすぎると、質問が唐突になったり、会話がぎこちなくなったりしてしまいます。相手が心地よく話せるリズムを意識しましょう。
情報を引き出そうとしてオープンクエスチョンを続けすぎると、考えながら話す負担で疲れさせてしまうかもしれません。逆に、クローズドクエスチョンばかりになると、テンポは良くても自由に話せないことでストレスを感じさせます。
大切なのは、キャッチボールのように自然な会話が続いているかどうかです。相手の反応を見ながら、自由に語ってもらう場面ではオープンクエスチョンを、合意形成を進めたい場面ではクローズドクエスチョンを使う。この切り替えが信頼関係を深め、有意義な対話につながります。
クローズドからオープンへつなげて円滑な会話を促進
商談やヒアリングで「何から聞けばいいか」と迷ったときは、答えやすいクローズドクエスチョンからはじめるとスムーズです。いきなり「事業の課題は何ですか?」と聞くと、相手は何から話せばよいか戸惑う場合があります。
まずは「現在、〇〇の業務でお困りの点はありますか?」と尋ね、相手が「はい」と答えたら「具体的にはどのような点でしょうか?」とオープンクエスチョンで掘り下げましょう。このように、クローズドクエスチョンで会話の入口を作り、そこから相手の言葉を拾って深掘りしていくと、自然に詳しい情報を引き出せます。相手に負担をかけすぎず、本音を引き出すためのテクニックのひとつです。
誘導尋問にならないよう注意する
クローズドクエスチョンを使う上で、特に気をつけたいのが「誘導尋問」のようになってしまうケースです。これは、自分の望む答えを得るために、意図的に質問を重ねてしまう状態を指します。相手が「意見を押し付けられている」と感じれば、信頼を損なう原因になりかねません。
たとえば、「この機能は便利ですよね?」「導入すれば間違いなく改善されますよね?」といった聞き方は、相手にプレッシャーを与えてしまいます。これでは、本心からの同意は得られません。
クローズドクエスチョンは、あくまで事実や意思を確認するために使うものです。自分の意見を含めすぎず、相手が「いいえ」と答える可能性も尊重しましょう。「いいえ」という返答も、相手の考えを知るうえで重要な手がかりになります。
まとめ
オープンクエスチョンは相手の本音やニーズを深く理解するための手法であり、信頼関係を築く助けになります。ただし時間がかかる場合や、信頼関係ができていない段階では答えづらいこともあります。
そのため、クローズドクエスチョンと組み合わせて使うのが効果的です。商談の序盤ではクローズドクエスチョンで会話をテンポよく進め、中盤以降でオープンクエスチョンを取り入れると、顧客理解と合意形成をスムーズに進められます。
会話の流れを意識しながら質問を選び、場面に応じて使い分けることで、成果につながる商談を実現できるでしょう。
『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする
以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本
監修者
クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。
営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。