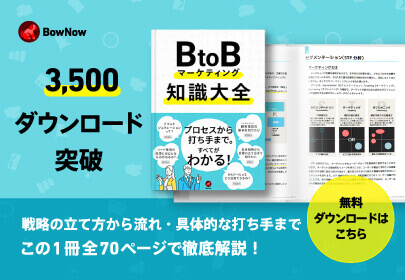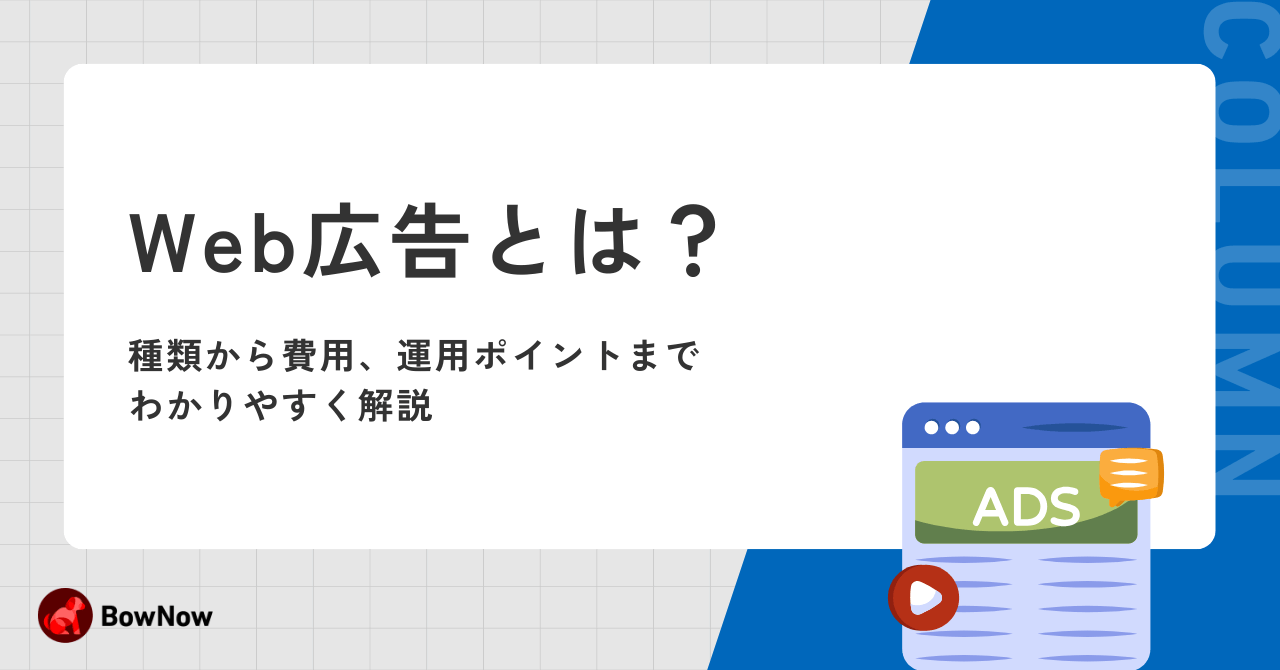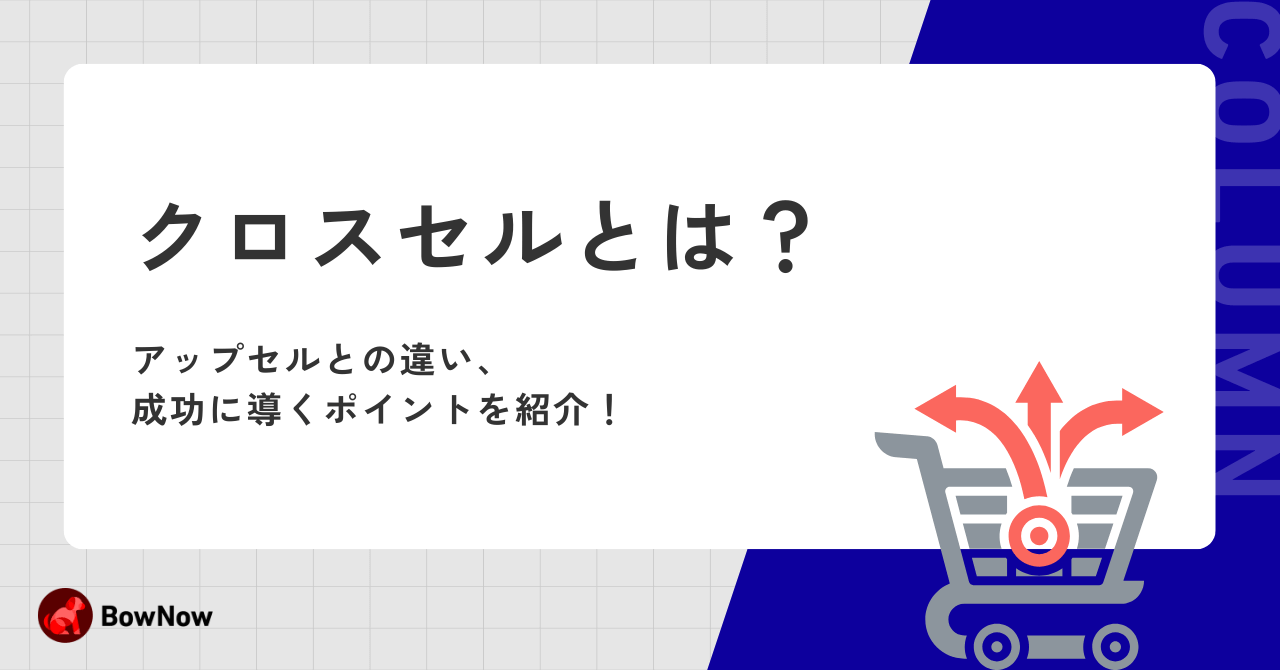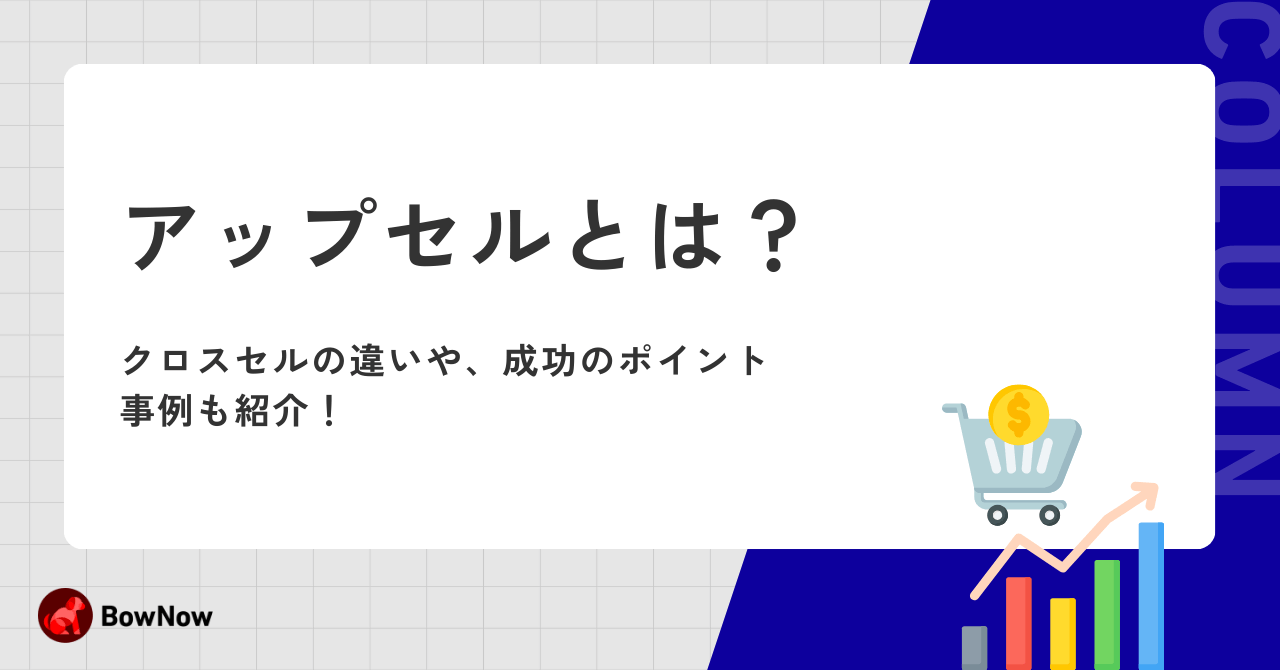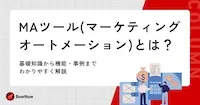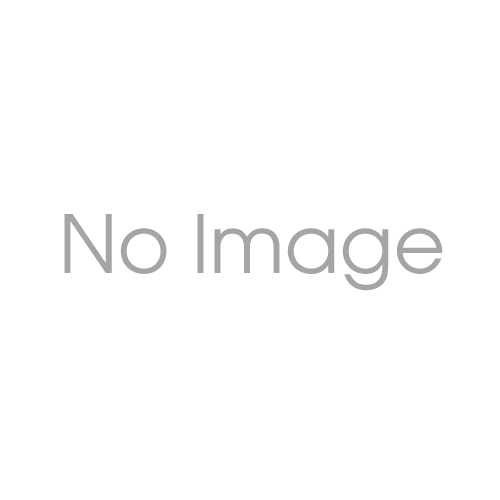MQLとは?SQLとの違い・質を上げるポイントなど徹底解説
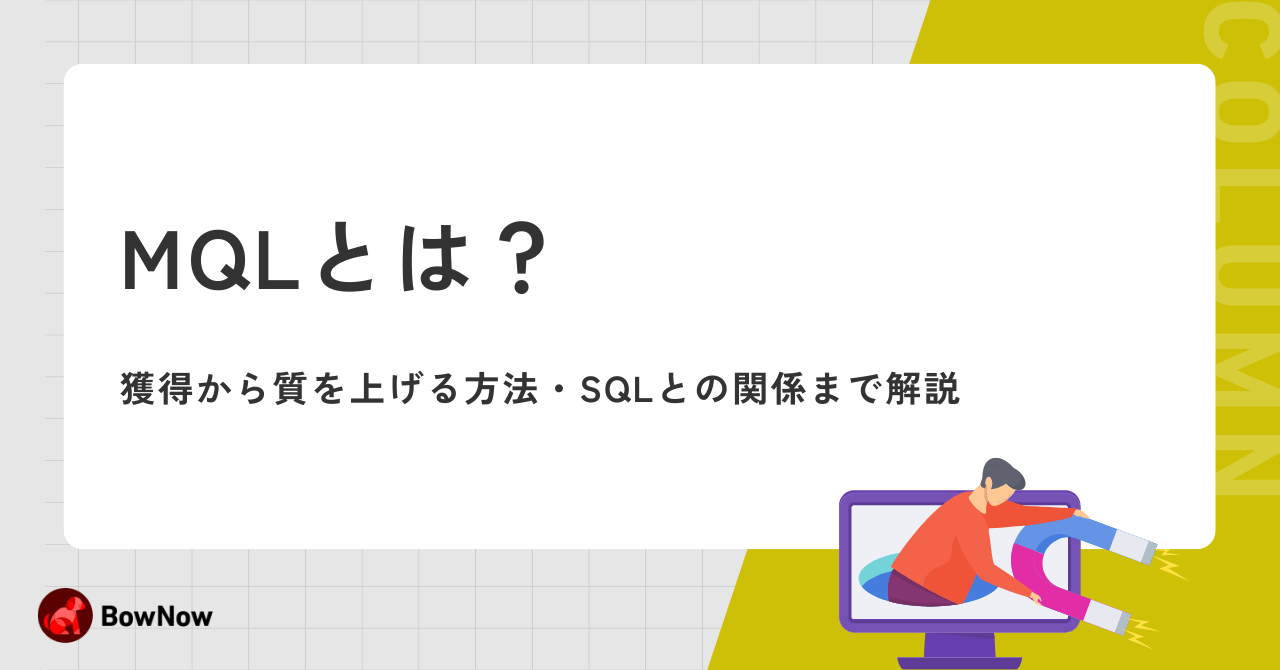
MQLとは、「マーケティング部門が創出したホットな見込み顧客」を意味する言葉です。マーケティングや営業活動でよく使われます。似た用語にSQLがあり、MQLを使う場合はSQLの理解が欠かせません。
この記事ではMQLについてやMQLとSQLの違いのほか、MQLでありがちな課題やその解決方法などを紹介します。
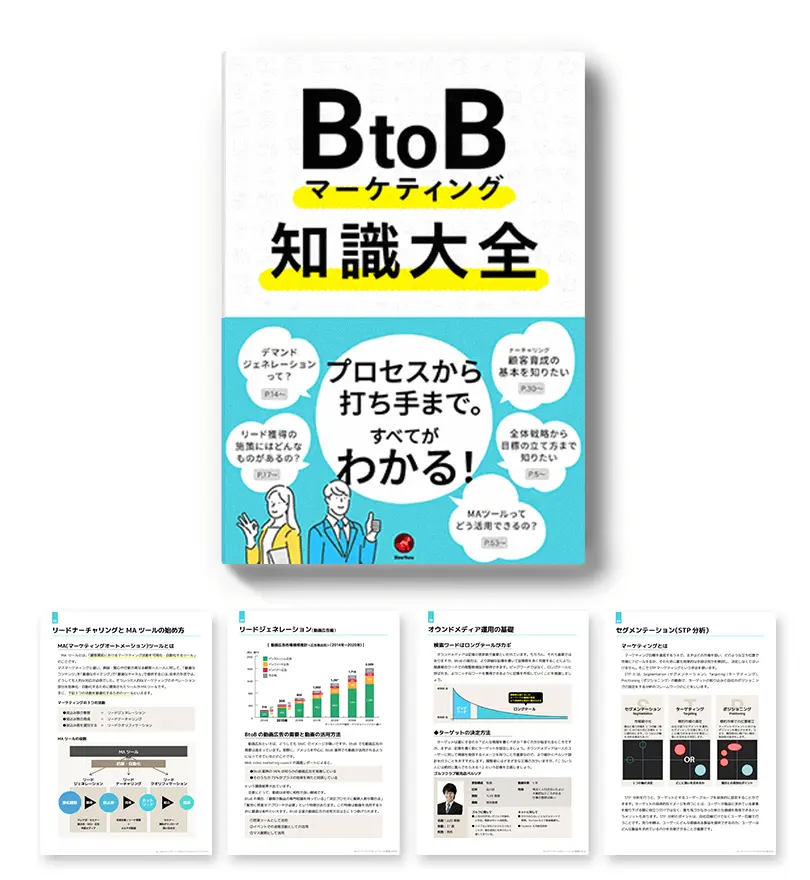
3,500ダウンロード突破!
『BtoBマーケティング知識大全』
BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。
まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。
目次
MQLとは
MQLとは、Marketing Qualified Lead(マーケティング・クオリファイド・リード)の略称で、「マーケティング活動で得た優良な見込み顧客」を指す言葉です。
イベントや展示会で獲得した情報を基に、メルマガやセミナーを行い顧客を育成し、購買意欲を高めた顧客のことをMQLと言います。「検討度合いが高く、優先して営業がアプローチをしてほしい顧客」「営業接触のための準備が完了している顧客」という意味があります。
なぜMQLを獲得するのか
MQLはなぜ獲得する必要があるのでしょうか?理由は4つあります。
効率的な営業活動を行うことができる
マーケティング活動でMQLを獲得し、受注確度の高いリードに育成できれば、ターゲットに対して無作為にアプローチをする飛び込み営業やテレアポといった、営業担当者に負荷のかかる営業活動を行う必要がなくなり、効率的に売上を獲得することができるようになります。
LTVの高い顧客からの受注に繋がる
テレアポや飛び込みといった活動で接点を持った顧客からも、もちろん成約は生まれます。しかし、MQLとして獲得するリードには、自社の製品やサービスに興味を持つ可能性の高いリードが、比較的多く含まれている傾向にあります。そのため、短期で成約に至る可能性があり、かつ製品やサービスの利用目的や目標を理解して検討している顧客も存在するため、契約後も解約されずらく、LTVも高くなる傾向にあります。
企業の売上拡大に、MQLの獲得は非常に重要
「売上が思ったように伸びない」「営業担当者の生産性が低い、目標を達成できない」「テレアポや飛び込みといった活動を続けてきた結果、若くて優秀な社員が辞めてしまった・採用できなくなってしまった」といった悩みを抱える企業は、マーケティング活動を通してMQLを獲得し、効率の良い営業活動を行うことをおすすめします。
また、上記のような悩みがない企業でも、近年はBtoBでも顧客の購買行動が変化しており、インターネットやSNSといったオンラインのチャネルを活用し、顧客を獲得することの重要性が高まっています。競合と差をつけ、現在よりも更に売上を獲得していきたいといった場合にも、マーケティング活動の強化とMQLの獲得は有効です。
MQLとSQLの違い
MQLとSQLはどちらも見込み顧客を指す言葉ですが、MQLは「マーケティング部門が生み出したホットな見込み顧客」、SQLは「営業が対応すべき案件がある見込み顧客」と意味が異なります。MQLの次のステージがSQLです。
まずマーケティング部門が、MQLと認定したリードに対して、セミナーやメールなどを活用して購買意欲を高める活動「リードナーチャリング」を行います。そして、マーケティング部門が購買意欲を高めたリードが、営業部門に引き渡されるとSQLになります。
SQLとは
SQLとは、Sales Qualified Lead(セールス・クオリファイド・リード)の略称で、「営業活動で得た見込み顧客」「インサイドセールスがニーズを確認し、営業に引き渡せる見込み顧客」を指す言葉です。日本語では「引き合い」とも言います。SQLは、求めるものや要望が明確で、導入時期が決まっている、導入予定があるなど購買意欲が高い顧客を指します。
マーケティングと営業部門の連携が重要
MQLとSQLを創出するには、マーケティング部門と営業部門(IS部門がある場合はそこも)の連携が必要です。しかし多くの企業では連携が上手くいかないという課題を抱えています。
というのも、SQLは顧客主導案件であり、価格交渉や納期調整などをすれば大抵クローズできる一方、MQLはマーケティング活動で創出した顧客のため明確な要望が固まっておらず、クローズまでに時間がかかります。SQLの方が営業が楽なので、営業部門はSQLを優先的に扱いたいと考えるのです。
また営業部門では目標達成が重視されるため、数をこなしにくいMQLは敬遠されてしまうこともあります。
マーケティング部門としては「ホットリードであるMQLを扱ってほしい」、営業部門としては「すぐ案件になるものだけほしい」というすれ違いが起きてしまうのです。また連携が上手くいかないと、必要な顧客情報が引き継がれない場合があります。営業としては、必要な情報が欠けていると扱いに困り「対応したくない」と思うでしょう。マーケティング部門としては営業がどのような情報を求めているのかわからず「引き継いだのは良いが、進捗報告がないためどうなっているのかわからない」、という悪循環に陥ることも。
こういったすれ違いを解決するには、マーケティング部門と営業部門共通の定義でリストを管理して進捗を共有し合うことが重要で、両部門の協力が不可欠です。
MQLとSQLを創出する手順
MQLとSQLを創出する手順について、順を追って解説します。
見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)=MQLの獲得
MQLを獲得する手法は様々ですが、BtoBで代表的な手法は「展示会」「セミナー」「SEO」「Web広告・SNS広告」などがあります。ただし、これらの手法を用いれば、どんなリードでも獲得すれば良いわけではありません。
前述でもご紹介したように、MQLは「マーケティング活動で得た優良な見込み顧客」です。MQLの獲得を始めるときは、事前に「自社にとってのMQLの定義」を明確にしたうえで、手法を選んでいくことをおすすめします。定義に合致しないMQLは、いくら獲得しても成約に至る可能性は低く、ただ組織の予算を無駄に浪費し、徒労に終わることになります。
見込み顧客の育成(リードナーチャリング)=MQLのSQL化
MQLの中には、獲得してすぐに商談や成約に至る顧客もいます。ただし、それらは獲得したMQLの一部です。通常、リードジェネレーションでは、自社のMQLの定義に合致する顧客を見つけ、関心をひき、定期的に連絡をとるための情報(氏名や連絡先など)を獲得するまでにとどまります。そこから、自社の製品やサービスに明確に興味を持ってもらい、ニーズを引き出すことが重要となり、その過程のことをリードナーチャリングといいます。
リードナーチャリングの手法は様々ですが、一般的にはMAツールという専用のツールを用いながら行います。メルマガの配信やセミナーの開催・集客といった手法を駆使して、ユーザーが自社の製品やサービスに関心を持つきっかけ(接点)をつくっていきます。
見込み顧客の絞り込み(リードクオリフィケーション)=SQLの絞り込み
リードナーチャリングによる継続的なコミュニケーションを経て、自社の製品やサービスに明確に興味を持った顧客や、購買を検討する見込みのある顧客をSQLとして抽出します。
近年SQLは、インサイドセールスという内勤で営業活動をする専門部隊がアプローチし、顧客に商談の設定を承諾させることが多いです。商談の日時を固め、場設定した状態で、商談・提案・クロージングを担当する外勤の営業部隊に引き渡します。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』
この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本
MQLをSQLに変えるためのポイント
MQL(マーケティングで見込み度が高いリード)をSQL(営業が商談可能と判断したリード)に変えるためには、マーケティング部門と営業部門の連携が重要です。以下に、そのポイントを解説します。
MQLの定義をマーケティング部門とすり合わせる
まず、MQLの定義をマーケティング部門と営業部門でしっかり話し合いましょう。「どんな人が商談につながりやすいか」「受注につながる見込み客とはどんな状態か」について、両部門で共通認識を持つことが大切です。営業部門の意見を取り入れることで、マーケティング部門は営業部門のニーズに合ったMQLを提供できるようになり、商談につながりやすくなります。
また、過去の商談データや受注率を分析し、MQLの判断基準を作ることも有効です。例えば、「過去6か月以内に〇〇というキーワードで検索した企業」「〇〇という展示会で名刺交換した企業」「〇〇という資料をダウンロードした企業」など、データに基づいた基準を設定することで、より確度の高い見込み客を営業部門に引き渡せるようになります。
SQLの定義を営業部門とすり合わせる
次に、SQLの定義を営業部門とマーケティング部門ですり合わせます。具体的には、「どんな条件を満たせば商談可能と判断するか」「購買意欲を示す具体的な指標は何か」などのSQLの定義を両部門で明確にします。例えば、営業部門がSQLと判断する条件として、「具体的な課題やニーズをヒアリングできている」「予算や導入時期について話が進んでいる」など、明確な基準を設定することが求められます。SQLの条件を定めることで、マーケティング部門がSQLに近い状態のMQLを生み出しやすくなり、営業部門での商談成立率が向上します。
SQLの判断基準は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直すことも大切です。市場環境や商品・サービスの変化、営業部門からのフィードバックに応じて基準をアップデートし、より精度の高い見込み客管理を行いましょう。
期間を定め、SQLにならないMQLはマーケティング部門に返す
SQLにならないMQLを放置すると、せっかく獲得した見込み客が埋もれ、ビジネスチャンスを逃してしまうことになります。営業部門がMQLを引き継いだものの、一定期間内にSQLに至らなかった場合は、マーケティング部門に戻す仕組みを作りましょう。マーケティング部門に返却された見込み客は、育成(ナーチャリング)を行い、購買意欲を高めてから再度、営業部門へ引き渡します。例えば、返却された見込み客には、以下のような施策を行います。このプロセスを仕組み化することで、MQLの質を向上させ、営業部門への適切なタイミングでの引き渡しが可能になります。
- メールで、見込み客の関心が高い情報を継続的に提供する
- 資料や導入事例を配信し、検討段階を進める
- セミナーやイベントに招待し、直接の接点を増やす
部門間の情報提供・連携を強化する
MQLを効果的にSQLに変えるためには、マーケティング部門と営業部門の情報共有を強化することが不可欠です。例えば、マーケティング部門は、創出したMQLがSQLに変わったのか、受注まで至ったのかフィードバックを得ることで、マーケティング施策の効果を検証できます。また、営業部門は、マーケティング部門がどんなアプローチを行ったかを理解することで、商談や契約の成功率を高められます。
連携を強化し、こうした取り組みを定期的に行うことで、MQLからSQLへの転換率を向上させ、より効果的な営業活動が可能になります。詳細に顧客の動きを管理したいなら、顧客管理システム(CRM)や営業支援ツール(SFA)、マーケティングオートメーションツール(MAツール)などの活用もおすすめです。見込み客の進捗をリアルタイムで共有することで、営業部門との連携を強化できます。
MAツールの活用で自動化・効率化しよう
リードジェネレーションで獲得したMQLを、効率的に育成し、SQLになったタイミングで抽出できるツールとして、MAツールがあります。特に、BtoBのリードナーチャリングやクオリフィケーションにおいて非常に役に立ち、導入する企業も年々増加しています。一体どういったツールなのか、本章で解説します。
MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは
MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは、リード情報を登録した顧客への定期的な情報発信や、検討確度が高まったタイミングで自動で抽出する業務を、自動化もしくは効率化するツールです。
条件に合わせて、様々なメルマガを送り分けたり一斉に配信することで、対象者に効果的に情報提供を行うことができます。また、対象者のメルマガの購読状況や、Webサイト上の動きをデータで可視化することができ、対象者の行動に合わせたアプローチを行うことができます。
検討確度が高まったタイミングで自動で可視化し、通知で知らせてくれるため、SQLとなったタイミングを逃すこともありません。継続的に運用しつづけることで、着実に会社の売上や利益の創出に貢献することができます。

MQLからSQLを簡単に創出できる!MAツール『BowNow』

はじめてMAツールを運用し、リードの育成やSQL化に取り組む際におすすめのMAツールが、『BowNow(バウナウ)』です。現在全国で14,000社以上に導入されています。マーケターも営業担当者も使いこなせるMAを目指して開発されており、使いやすさに定評があります。
メルマガでの情報発信も、あらゆる設定から選ぶことができる他、ABMテンプレートという独自の機能により、事前に複雑な設定をしなくても、検討確度の高いリードが現れたときに自動でダッシュボード上に可視化することができます。サポート体制についても手厚く、運用の目的と目標に合ったフォローをCS担当者が行うため、はじめてMAツールを導入する場合にも、安心して継続的に活用することができます。
MQLからSQLを生み出す!MAツールの活用例
MAの導入により、営業部門とマーケティング部門が共通した条件でリードを管理でき、適切なタイミングでアプローチできるようになります。ここでは、MQLからSQLを生み出す、MAツールの効果的な活用例を紹介します。
スコアリングを使用する場合
MAツールでは、見込み度の高いリード(ホットリード)の共通定義を作り、リストを管理することができます。やり方はいろいろありますが、例えばMAツールのスコアリングを活用し、見込み顧客のアクションごとに点数をつけて合計スコア〇点以上をホットリードとする、という方法がよく見られます。
マーケティングノウハウがあり「どういったアクションをとっているユーザーが受注につながりやすいか」をきちんと分析できている場合は、スコアリングを活用することで商談創出活動をかなり効率化・自動化できます。
ABMの考え方に沿っておこなう場合
ABM(アカウントベースドマーケティング)という考え方に基づき、ポテンシャルとステータスのマトリクスでホットリードかどうかを判別する方法もあります。
この方法のよいところは、ステータスが高くてもポテンシャルが低ければマーケ部門がまとめて対応でき、逆にステータスが低くてもポテンシャルが高いところは営業をアサインするなど、柔軟な対応ができることです。営業とマーケティングの連携がスムーズになり、効果測定もしやすくなります。

関連記事:ABMテンプレートとは?
特定のアクションを行なったリードをホットリードと定義する場合
見積もり依頼など、今までのデータをみたときに非常に受注率が高いアクションがある場合、そのアクションをとった顧客をホットリードとして定義する方法もあります。ページのコンテンツが多くない、またはマーケティング活動を始めたばかりの場合は、まずここから初めてみるのもよいでしょう。
MAの活用で部門間のすれ違いをなくす
MAツールを活用することで、部門間のすれ違いをなくし、商談数の最大化を目指せます。しかし一般的なMAツールは、機能や設定が複雑で使いこなせないことが多いです。そういった場合は、マーケティング初心者の方でも使いやすい機能やサポートを揃えたMAツールの導入をおすすめします。
まとめ
MQLを創出することで、営業活動を効率よく行うことができます。MQLから見込みとなった顧客は、マーケティング活動を通して自社のことをある程度信頼してくれているため、リピーターになるケースも高まります。MQLをSQLに引き上げ効率的に営業を進めるには、マーケティング部門と営業部門の連携が必要不可欠。しかしいきなり連携をしようとしてもなかなか上手くはいきません。そこでMAツールを使い、共通した条件でリードを管理をおこないましょう。
『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする
以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本
監修者
クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。
営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。